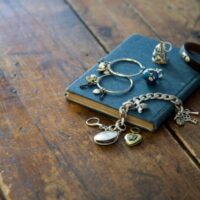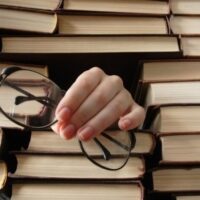ページに広告が含まれることがあります。
今回は、紙を持ちすぎずに暮らすポイントを7つ紹介します。
紙は家の中に入ってきやすいもの。
チラシやプリント、レシート、明細書など、1枚だけならたいしてかさばりませんが、ためてしまうと山になり、必要なときに探せなくなります。
紙類を整理する方法がよく話題になりますが、家に入ってくる紙そのものを減らして、ためこみすぎなければシンプルな管理で間に合います。
以下に紙をためこまない基本的なやり方を紹介しますね。
どれもちょっとしたことですが、継続すれば紙のストレスが減ります。
1.紙を持ち込まない
紙をためない暮らしをするために一番重要なのは、不要な紙を家の中に持ち込まないことです。たくさん入ってこなければ、管理や整理、処分をする手間もありません。
郵便受けに入っているチラシやDMは、その場で確認して不要ならすぐに処分します。
「あとで読むかも」と、家の中に安易に入れないようにしましょう。気になる箇所があるなら、その場で写真を撮っておけば、いつでも参照できます。
スーパーやドラッグストアの特売情報は、今はアプリやウェブで確認できます。チラシを取っておく理由はありません。
レシートや領収書は必要なときだけ受け取りましょう。
受け取ったとしても、自宅に持ち帰らず、会計の直後にチェックしてその場で捨ててください。
家計簿をつけるのに必要なら、紙ではなくメールで送ってもらえばいいでしょう。近年は、電子レシートの導入が進んでいるので、積極的に利用しましょう。
最初から紙が届かないように工夫するのも効果的です。
ポストに「チラシお断り」のシールを貼れば、広告の投函が大幅に減ります。
街頭で配られるパンフレットや無料冊子は、お金を出して買いたいもの以外は受け取らないようにします。
学校やイベントで受け取った案内も、必要な部分だけスマホで撮影すれば十分です。
こうして入口で紙をブロックすることを習慣にしてください。
2.デジタルを活用する
日常で使う情報を、パソコンやスマホで確認しましょう。
本や新聞の購読は電子版を選べば保管場所が不要になり、読み返したいときも、検索ですぐに見つかります。スクラップや切り抜きの手間も要りません。
メモやアイデアを書き留める習慣も、紙の付箋やメモ帳ではなく、アプリに統一すると管理が楽になります。
クラウドに保存しておけば、外出先でも見られるので「どこに置いたっけ?」と探すこともなくなりますよ。
病院の診察券やポイントカードなどもアプリ化が進んでいます。できるだけデジタルで管理すれば、財布や引き出しに紙やカードをため込まずに済みます。
請求書も可能な限りオンラインで確認しましょう。
クレジットカードや公共料金、銀行の利用明細は、ほとんどがウェブ明細を利用できます。
日本では、意外にオンラインで銀行取引をする人が少ないようですが、スマホで行えば、支店やATMに行かなくてすむので、ぜひ試してください。
ペーパーレスを意識する~ガラクタを増やすライフスタイルをやめる(その6)
3.一時置き場をつくる
どうしても入ってくる紙には一時的に置いておく場所を作ります。
下駄箱やテーブルの端、棚の上などに無造作に置くとすぐ山になります。専用のトレイやクリアファイルを一つだけ用意しましょう。
量が多い人は、カゴバッグもいいですね。
入ってきた紙は、一時置き場だけに置き、家のあちこちに散らからないようにしましょう。
「あ、あれどこにあったかな」と思ったら、この置き場だけを探せばいいのです。
一時置き場にためた紙は、週末やゴミの日の前日など決まったタイミングで必ず空にしてください。ここがいっぱいになったら処理する、とルールを決めてもいいでしょう。
紙を置くスペースは小さめにしておくと、ためこみすぎません。
4.ざっくり分類する
家に入ってきた紙を整理する際に、複雑な仕組みにしないようにします。
おすすめは、ざっくり3つに分けることです。
・即処分する
・すぐ使って処分する
・しばらく保存する
捨てる紙は、一度見たら用が終わるものです。
すぐ使う紙は、請求書の支払いなど、わりとすぐに処理が終わるもの。
しばらく保存する紙は、長期間、保存が必要になる紙です。
分類をざっくりしておくと、整理している最中に悩む時間が減ります。
保存する紙も、必要なのが、紙そのものではなく、そこに書いてある情報ならば、スマホで写真を撮ってしまえば、紙はすぐに捨てることができます。
その紙に書いてあることをもとに行動する場合、できるだけ早くして、紙は処分してください。
・出欠の返事⇒予定を確認してすぐに出す
・請求書⇒すぐに支払う
・回覧板⇒すぐ隣に持っていく
こんなふうに行動を早めにしておくと、家の中にとどまる紙が減ります。
5.保存には期限をつける
それぞれの紙に、保存する期限をしっかり決めましょう。
いつまで取っておくか決めていないと、いろいろな紙を何年もずるずる持ち続けてしまいます。
たとえば、レシートや領収書は、家計簿に記入したら処分するとルールを決めておけば、紙はたまりません。
保証書は、購入から1年(保証期間が切れるまで)、学校や地域のお便りはイベントの終了後に処分と決めるといいでしょう。
捨てる期限がしっかりわかるように、紙に直接日付を書くか、付箋に書いて貼っておくことをおすすめします。
重要な書類も、無期限に残す必要があるものはそんなに多くありません。
税務関係なら7年、保険関係は契約中のみなど、公的に保存期間が決まっているので、それぞれ確認して、期限が来たら捨てるようにしてください。
私も、確定申告に必要な紙は、保存すべき期限がすぎたらすぐに捨てています(裏紙をメモに使えるものは、どんどん使ってしまう)。
6.メモは一元化する
手書きのメモは一箇所にまとめて書きましょう。
紙の山で意外と場所を取るのが、メモや付箋、思いつきの走り書きです。
あちこちにメモを残すと、どこに書いたのか探すのが大変なので、メモは一元化します。
やり方はシンプルで、書く場所をひとつに決めるだけです。
ノート一冊にすべて書き込む、スマホのアプリ(AppleのメモアプリやLineなど)にまとめて書き込んでください。
私は日常のメモは全部インデックスカードに書いて束ね、用が終わったらどんどん捨てています。仕事に関することは、Google Keepにメモしています。
どんな方法を使ってもいいので、分散させないことを意識してください。
7.ルールを共有する
紙の処分や管理のルールを家族にも伝えてください。
一人暮らしなら自分だけで完結しますが、家族と住んでいるときは、全員で紙をためないことを心がけたほうが効果的です。
自分は紙を増やさないようにしていても、家族がどんどん紙を持ち込んだり、そのへんに山にしたりすれば、よけいなストレスがたまります。
学校のプリントは必ず一時置き場に置く、不要なパンフレットは家に持ち帰らないなど簡単なルールを家族と共有してください。
家族の中に定期的に病院を利用する人がいるなら、医療関係の紙だけをまとめる封筒やフォルダーを用意します。領収書や薬の説明書などはすべてここに入れるようにするといいでしょう。
ルールを共有するコツですが、難しいルールにしないことが重要です。
ちょっと意識すれば、誰でもすぐにできる単純な決まりごとを、一つずつ導入していきましょう。
たくさんのことを要求すると、どのルールも定着しません。一番簡単で一番効果的なルールから始めてください。
◆関連記事もどうぞ
⇒今年中にやってしまいたい片付けプロジェクト(その3):紙ゴミを捨て切る。
⇒筆子流、紙ゴミを増やさない極意:ミニマリストへの道(70)
**********
紙をためこない暮らし方のコツを、7つ紹介しました。
一番おすすめしたいのは、必要な紙だけ家に入れることです。
紙をためないようにすると、部屋が片付くだけでなく、手に入れた情報をちゃんと使う生活に近づきます。
今回紹介した7つは、どれも難しくありません。紙を手にしたそのときに判断し、必要なものだけを残す習慣を身につけてください。