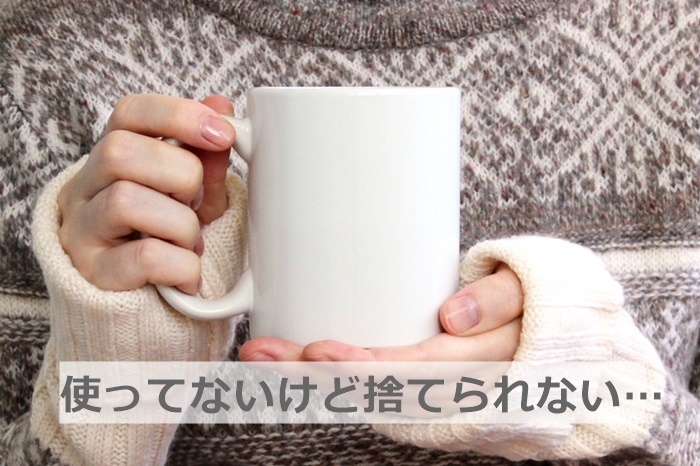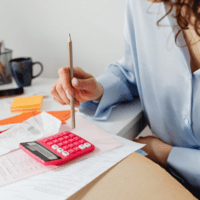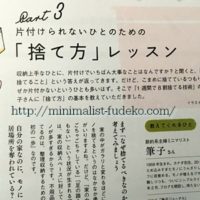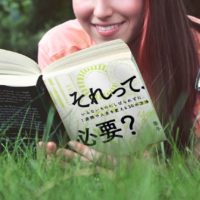ページに広告が含まれることがあります。
使っていようと、使っていまいと、もったいなくて物がなかなか捨てられない。こんなふうに感じること、よくあると思います。
こう感じる理由の1つは、「授かり効果」のせいである、と3年ほど前に記事にしました。
授かり効果は、物を所有すると、実際の価値よりも、より価値があると感じてしまう心理的傾向です。
無意識のうちに現状維持を好んでしまう性向のせいで、ガラクタを捨てられない人に、きっちり捨てる方法をお伝えします。
1.授かり効果について知っておく
まず、授かり効果という認知バイアスがあることを知ってください。
人間は、何かを所有すると、必要以上に価値があると感じてしまうんだな、スッキリした環境に住むという望ましい未来への可能性よりも、ガラクタに囲まれて暮らす現状を選んでしまいがちなんだな。
こうわかっていると、何かを捨てられないとき、「待てよ? 自動的に大事な物に思えるだけなんじゃないの? 客観的に考えたら、がらくたなんじゃないの?」と考え直すことができます。
授かり効果の説明はこちら⇒物を捨てられないのは恐怖のせい~損失回避と、授かり効果の心理をさぐる
こちらでは、わかりやすいアニメーションの動画を紹介⇒なぜ人は、物に執着してしまうのか? 物と健全な関係を持つには?
授かり効果そのものは、べつに悪いことではないです。
所有したものの価値があがるからこそ、人は物やご縁を大事にすることができるのですから。
ですが、もういらない物を片付けているときは、「縁があって家に来たんだ、何もかもすべて大事にしよう」と考えてしまうと、何1つ、捨てることができません。
2.いまの自分が本当に欲しい物か、考える
所有しているという、その理由だけであがってしまった価値を見極めるために、いまの自分が本当に欲しいかどうか、考えてみます。
アクセサリーの整理をしていて、もう何年も使っていないネックレスが出てきたします。
そのとき、こんな質問をしてみてください。
いまの私が、これを買ったときと同じ値段で、きょう、また同じ物を買うだろうか?
いまの私が、これを買ったときに費やしたのと同じぐらいの労力を使って、きょう、また同じ物を買うだろうか?
もし答えが、「いいえ」だったら、それは捨てるべきものです。
いまの自分にとってもう必要ではないのですから。
「いや、買わない」と思いつつ、「でも、まだきれいだし、もったいない。そのうち使う時が来るかもしれないしね」と思うなら、もう1つべつの質問をするといいでしょう。すなわち、
いまの私は、どれだけの労力や時間、お金を使って、これを手に入れたいと思うだろう?
お金も時間もエネルギーも使いたくない、と思ったら、捨てても大丈夫なものです。
そのまま持ち続けると、これからもお金、時間、エネルギーを使うことになります。
所有するとコストがかかる話⇒節約ではお金はたまらない。お金持ちになりたいなら、買わない暮らしが1番いい
3.使うのに、どれだけ時間がかかるか考える
それぞれを実際に使い切るのに、どの程度時間がかかるか見積もってください。
洗剤や、ティッシュ、トイレットペーパー、パンストといった消耗品は、持っていればいつか必ず使うときが来ます。だから捨てない、という人はたくさんいます。
山のようにあって、スペースを圧迫していたとしても。
そんなときは、では、これだけ使い切るのに、どれだけ時間(日数、年数)がかかるのだろう? と客観的な予測をするのです。
言っておきますが、自分一人で使いきれる量はたかがしれています。
まだ30代なら、あと50年ぐらいは生きるでしょうから、使い切る時間はたっぷりあるかもしれません。
ですが、時間がたっぷりある人は、そのあいだに、生活環境が変わる可能性も見積もっておくべきです。
わたしは以前、音楽を録音したカセットテープを大量に持っていましたが、知らないうちに、メディアが変わって、すべて、ろくに聞かないまま、断捨離することになりました。
若い人は、カセットテープなんて知らないかもしれませんね。それが何なのか知りたい人はこちらを⇒捨てれば捨てるほど思い出が豊かになるカラクリとは?~カセットテープを断捨離して気づいた真理
さらに、自分の趣味嗜好が変わることもあります⇒人は変わり続ける。未来の自分に対する心理:ダン・ギルバート(TED)
先日、お菓子作りに使う道具を断捨離した話をしましたが⇒お菓子作りの道具を断捨離したきっかけとそのプロセス
お菓子作りが好きだったときは、自分はずっと、それこそ一生、この趣味を続けると本気で思っていました。
ですが現実は違いました。
趣味に使う材料も、せいぜい、3年ぐらいで使い切れる量にとどめておいたほうがいいと思います。「腐るもんじゃなし」とは、物を捨てない私の母がよく言うことですが、腐らなくても、劣化はします。
私のように、60歳近い人は、使い切る時間はそんなに残されていないので、よりシビアに、使い切れる量を判断すべきです。
物を使い切ることの難しさがわからない人は、一度、ターゲットを決めて、何かを使い切ってみるといいでしょう。
ボールペンでもいいし⇒持たない暮しをめざすなら、ぜひマスターしておきたいボールペンを使い切るコツ
食料品でもいいです⇒パントリーチャレンジのススメ~ズボラ主婦だからできる究極の節約方法
ためこんでいるコスメのサンプルでもいいです。使い切るの、大変ですよ。
4.必要度合いを客観的に考える
それは本当に必要なのか、客観的に考えてください。
物はお金と似ているところがあります。ともに、使ってはじめてその価値を発揮できます。
使わないでそのままにしておいても、何の価値も生み出しません。
まあ、お金は、あれば、安心感をもたらしてくれるし、いま使っていないからといって、どんどん使えばいい、というものでもありません。使いみちをしっかり考えないと、価値は生まれません。
ですが、物はどうでしょうか?
使わないでためておいても、邪魔なだけで、安心もへちまもありません。
物はどんどん使うべきだと思います。
飾り物は、しまいこまずに、ちゃんと飾ったほうがいいでしょう。思い出の品だって、ときどきはひっぱりだして、思い出にひたったほうがいいんじゃないでしょうか?
そのために、捨てないで持っているのですから。
何かをもう何年も使っていないとしたら、その一番の理由は、「使う必要がないから」だと思います。
ここ数年使う必要のなかったものが、この先、必要になることが本当にあるのでしょうか?
2番でも言いましたが、生活環境はどんどん変わります。
たとえ、自分は変わらないつもりで、来年も再来年も、だいたい同じような生活をキープできたとしても、10年、20年というスパンで見ると、ずいぶん大きく変わるものです。
20代の半ば頃、3種類の全集を持っていました。筒井康隆、村上春樹、森茉莉の全集です。村上春樹と森茉莉は、ともに8巻ぐらいなので、たいしたことないのですが、筒井康隆は24巻もありました。しかも、活字は二段組。
ほかにも本はたくさんあったため、ほとんど読まないまま、時間がすぎていきました。
「なかなか読めないんだよね」と友達に言ったら、「うん、まあ、老後の楽しみに」と言われました。
あれから、30年近く時が流れ、私はまだ老後ではありませんが、もはや自分が筒井康隆全集を読むなんて想像できません。そんな時間はなさそうですし、そもそも、全集を手元に置きたいとも思いません。
客観的に考えてみると、ここ数年読んでいない本は、この先も読まないし、使っていない物はこの先も使わない可能性のほうが高いのです。
つまり、必要ないものがいきなり必要になることはまずないのです。
少なくとも、新しい物をどんどん家の中に入れていたら、そんなことは起こりません。
家の中に入ってこようとする物をシャットアウトして、すでに中にあるものをしっかり使おうと意識しない限り。そうするのは、そんなに簡単なことではないのです。
******
今回は、授かり効果のせいで捨てられない物を捨てられるようになる考え方をお伝えしました。
いったん、自分の物にすると、捨てるのは心身ともに大変なので、新しい物を導入するときは、くれぐれも注意してください。
特に、「無料のもの」と「安い物」は要注意です。たとえ、ただでもらった物でも、100均で買った物でも、同じように授かり効果が発生します。
いま、物余りに悩んでいる人が多いのは、いろいろな物がきわめて安く簡単に手に入るせいです。必要以上に、使い切れないほど、家の中に入れるから、片付けに悩むのです。