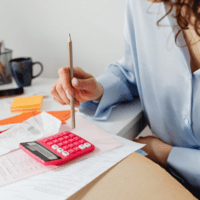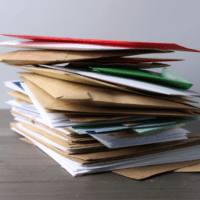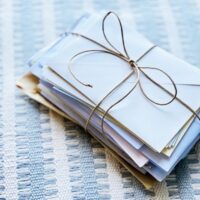ページに広告が含まれることがあります。
贈り物を捨てるときに抱いてしまう罪悪感とうまく折り合いをつける方法を7つ紹介します。
もらったときはうれしかったプレゼントでも、時間がたつと使わなくなったり、置き場所に困ったりすることがありますよね。
いざ処分しようとすると、「捨てたら悪い気がする」「相手に申し訳ない」と感じて、なかなか手放せず、そのままずるずる持ち続けてしまう──そんな経験は誰にでもあると思います。
けれども、どんなに気持ちのこもった贈り物でも、今の自分の暮らしに合わなくなったなら、無理に持ち続ける必要はありません。
気持ちの負担になっていると気づいたら、以下のように考えて、思い切って手放してください。
1. もらったときに贈り物の役割は終わった
贈り物は、自分が受け取ってお礼を言った段階で役目を果たしたと考えてください。
どんなものも、ずっと使い続けることは難しいものです。
生活が変われば必要なものは変わります。以前は出番が多かったものが、今の暮らしには合わなくなることはよくあります。
たとえば、今、日本は夏が長いので、以前は使った秋物の服の出番は減っているでしょう。
自分の好みが変わることもあります。
「せっかくのプレゼントだから」と無理に持ち続けようとするのは、合理的ではありません。
「この贈り物は、あのとき私を喜ばせてくれた。もう十分に働いてくれた」と考えて手放しましょう。
2. 感謝は行動で伝える
もらったものをずっと持ち続けることで、感謝の気持ちを示そうとするのはやめましょう。
「ありがたい」と思う気持ちは、別の形で伝えてください。
「あのときお祝いしてくれてうれしかった」「覚えていてくれたことに感謝している」。こんな気持ちが伝わるような行動をしましょう。
たとえば、相手の近況を気づかったり、誕生日にメッセージを送ったりします。
お茶を飲んだり、食事をしたりして、共に時間を過ごすのもいい方法です。
相手が喜ぶ行動をすれば、思いは十分伝わります。
感謝の気持ちは、いらないものを無理に残すことではなく、いい関係を築ける行動に込めてください。
3. ものと気持ちを切り離す
プレゼントに込められた思いや、相手との関係に対する気持ちを、ものと切り離して考えましょう。
贈り物を捨てると、大切な気持ちまでなくなってしまうと考えると、もらったものを手放しにくくなります。
ものと気持ちは違います。
たとえば、プレゼントにもらったぬいぐるみを捨てたからといって、その人との関係が終わるわけではありません。
お土産として友人からもらったマグカップを手放しても、思い出や信頼関係は変わりません。
むしろ、いらないものを無理して抱え込もうとすると、「こんなものをくれるなんて」と相手に恨みがましい気持ちを感じてしまうかもしれません。
「気持ちは心にある。ものは役目を終えた」。こう考えて、プレゼントを捨てる迷いを解消しましょう。
4. 使わないことは罪ではない
もらったものを使わないことを、「悪いことだ」と考えるのはやめましょう。
使わないことは罪でも何でもありません。
贈り物は、自分ではなく、相手が選んだものです。
自分の生活や好み、タイミングにぴったり合うものをもらうほうがまれではないでしょうか?
デザインが好みでないスカーフ、苦手な香りの入浴剤、自分の部屋に置くには派手すぎる花瓶。気持ちはうれしくても実際には使いづらいものはたくさんあります。
こうしたアイテムを無理に使おうとするより、「自分の生活には合わない」と考えて、よそに回す方がいいです。
これは自分が「冷たい」ということではなく、現実に即した判断です。
贈り物を使わないことに罪悪感を持つ必要はありません。
5. 贈り主の意図を考える
贈り物の多くは、相手を幸せにしたい、喜ばせたいという気持ちから渡されたものです。
この場合、自分が心地よく暮らせる選択をすることが、いちばんのお返しになります。
「使わないけど捨てるのは悪い」と悩むのは、相手の意図を誤解していると言えます。
贈り主は、それを一生使い続けてほしいと願ったわけではなく、相手に「笑顔になってほしい」と思って選んだのです。
使わないものを無理に持ち続けることは相手の意図に反する行動です。
もう一つ、相手の感情を完全にコントロールすることはできない、という考え方も重要です。
贈り主に、「未来永劫これを使ってもらいたい」という気持ちがあり、そうならないことを知って残念に思ったとしても、それは、私たちにはどうすることもできません。
他人の感情の処理は、本人に任せましょう。
6. 写真や文章で残す
もう使わない、でもとても捨てにくい贈り物は、写真や文章で残しましょう。
私たちは、贈り物そのものではなく、そこに込められた出来事や感情、相手との関係を重要視しています。
だから、写真や文章でその気持ちを残せば、ものを手放しても思い入れを失うことはありません。
たとえば、スマホで撮影して、短いメモを残すといいでしょう。
iPhoneなら写真を開いて「i」マークを押し、「キャプションを追加」の欄に「〇〇さんからのプレゼント」「この時計をもらったとき、うれしかった」などと入力できます。
Googleフォトでは「説明を追加」に同様のメモを残せます。
写真アプリのメモ欄が使いづらいなら、写真をメモアプリに貼り、もう少し長い文章を残すのもいいと思います。
こうして記録を残せば、ものがなくても、贈り物をもらった事実を忘れることはありません。
7. 今の暮らしを優先する
贈り物を手放すかどうか迷ったら、「今の自分に必要かどうか」で判断してください。
結局一番重要なのは、今、自分が快適に暮らすことです。
贈り物には、どれも特別な思いが込められていますが、もらった贈り物を全部残そうとすると、暮らしにくくなります。
不用品が増えれば増えるほど、管理、掃除、整理の負担が増えますし、今使いたいものや、本当に大切なものが埋もれてしまいます。
時間もスペースも限られているので、必要なものだけを持って暮らすことがベストの選択です。
そういう生活を心がけるのは、結果的に、贈ってくれた人の願いに叶うと思います。
贈り物に込められた好意は大切にしつつも、生活の基準は「今」に置きましょう。
贈り物を捨てにくい人が読む記事
贈り物を手放す勇気を持て:本質を理解すれば罪悪感もないし、断捨離も簡単になる。
豪華なプレゼントはいらない~人を特別な気分にさせる秘訣(TED)
*****
贈り物を捨てるときに生じる罪悪感の手放し方を紹介しました。
贈り物は、気持ちを受け取った時点でその役目を終えています。手放しても、相手に対する感謝の気持ちは消えません。
使わない贈り物は、心の中で「ありがとう」と言ってから手放すといいでしょう。
リサイクルショップや寄付を利用して、使ってくれる人の手に渡せば、死蔵品だったものが、役立ちます。
捨てることに罪悪感を抱くのではなく、贈ってくれた気持ちに感謝して、今の暮らしを整えることを考えてください。
それは、悪いことではありません。
使わない贈り物を処分して、身の回りを整えると、日々の暮らしに余裕が生まれます。