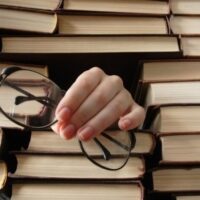ページに広告が含まれることがあります。
海外では、日本は「静けさの中に美がある国」というイメージがあります。ある種の理想のイメージですが、言うまでもなく、日常の日本の暮らしとの間にギャップがあります。
今回はそのギャップを通じて、暮らしを整えるヒントを探っていきます。
一般に海外では「日本の暮らし」はシンプルライフだと思われています。
すっきり片付いた部屋や、静かで整ったライフスタイルを思い浮かべる人が少なくありません。
シンプルさや調和を大切にする姿勢は、メディアでたびたび紹介され、世界中の人々の憧れの的です。
でも、日本で実際に暮らしている人たちからすると、現実とは違う部分もあるのではないでしょうか。
多くの家庭ではものが増えすぎたせいで困っており、片付けに追われているのが実情です。
理想と現実の差をたどりながら、なぜギャップが生まれるのか、そこから何を学べるか見ていきましょう。
「日本=シンプル」のイメージ
海外で日本の暮らしが紹介されるとき、しばしばシンプルであることが強調されます。
余計なものを持たず、少ないもので整然と暮らす姿は、静けさの中に心の平穏を見いだすライフスタイルです。
雑誌やSNSには、すっきり片付いた和室や、無駄のないインテリアの写真が並び、「日本人は皆こうした環境で暮らしている」という印象を与えます。
都市部の住宅事情のせいで、限られたスペースを効率よく使わざるを得ない日本の暮らし方が「洗練されている」と見られることもあります。
日本特有の美意識である「わびさび」や「禅」も、日本を紹介するときのキーワードです。
わびさびは、不完全さや古さの中に美を見いだす考え方で、使い込まれた器や色あせた木の質感を楽しむものです。
禅は、静けさや心の調和を重んじる思想として知られ、シンプルな生活と結びつけられます。
こうしたコンセプトは、控えめで奥ゆかしい日本文化の象徴であり、欧米の人々にとっては新鮮です。
日本発の「片付け術」も、日本の暮らしを語るうえで外せません。
近藤麻理恵の、ときめきで選ぶ片づけ術を説く本は、世界中でベストセラーになり、日本人=片づけ上手という印象を強めました。
こうした紹介を見るとき、私は、「確かにそういう面もあるが、日常生活の実態とは違う」とよく思います。
実際の日本の家庭はどうか?
私の経験では、実際の日本は、ものをたくさん持って暮らすことが一般的だと思います。そうでなければ、こんなにたくさんの片付け本や断捨離本は発売されないでしょう。
現実は、以下のようではないでしょうか?
実際の住宅事情
都市部の住宅はコンパクトで収納スペースも多くありません。それなのに、人々は家電や衣類、日用品をたくさん持っています。
その結果、居住空間が狭くなり「片付けてもすぐ散らかる」と思っている人が多いです。
高齢化が進む今、親世代が残した大量の持ちもの処分に苦慮する人も目立ちます。
「もったいない精神」の裏返し
日本にはものを大切にする価値観を表す「もったいない」という独特の言葉があります。
これはいいことですが、捨てずに取っておくことが大切にすることだと考えがちです。そのために、食器や衣類、古い家電をいつまでも取っておき、家の中にものがあふれます。
片付け情報は多いが実践されない
メディアでは「こんまりメソッド」をはじめとした片付け術が広く紹介されています。しかし、実際に片付けが習慣として根づいている家庭はそんなに多くありません。
たぶん、みんな忙しいからでしょう。仕事や子育てに追われて片付ける時間がとれず、大量のものの中で暮らすことを余儀なくされます。
買い物を続けるライフスタイル
日本ではかわいいもの、便利なものが市場に豊富に出回っていて、買うハードルも低いです。
私はカナダのダラーストア(いわゆる百均)では、心をそそられるものをなかなか見つけられません。しかし、日本の100均や300円ショップなどでは、かわいいと思う雑貨がたくさんあります(買いませんが)。
買い物しやすい社会では、どうしてもものを持ちすぎてしまいます。
こうして見ると、日本の家庭は、海外の人が感じるシンプルライフやミニマリズムとはずいぶんかけ離れています。
なぜイメージと現実にギャップがあるのか?
次に、日本のイメージと実態になぜギャップが生じるのか見ていきます。以下のような理由が考えられます。
メディアや観光客が切り取る「特別な場面」
海外の人が目にする日本は、旅行や雑誌を通じた一部分です。
寺院や庭園、伝統的な和室など、整然として美しい場所は実際に存在し、観光客の印象に強く残ります。けれども、そうした場面は日常ではありません。
旅行者は物置となった部屋や雑然としたリビングを目にすることはなく、美しい部分だけを心に刻みます。
文化の輸出と自己演出
日本人自身も、海外に向けて発信するとき、わびさび、禅、ミニマリズムといった洗練された文化を前面に押し出す傾向があります。
茶道や生け花など、整った形式美をともなう文化は紹介しやすく、生活そのものを見せるより優先されるでしょう。
そうやって、「日本人は皆このように暮らしている」というイメージが広がります。
伝統文化と日常生活の分離
わびさびや禅といった考え方は確かに日本文化の一部ですが、それがそのまま今の家庭の日常に浸透しているとは限りません。
伝統文化は茶室や寺院の中で守られていても、現代の家庭生活では必ずしも活かされないのです。
外から見ると象徴的な文化と日常は同じだと思いがちですが、実際には両者は別物として存在しています。
例外が理想像を強める
世界的に有名になった片付けの専門家や、ミニマリストとして注目される個人の存在も、イメージを固定化する要因です。
ほんの一部の実践者の極端な暮らしが紹介され、「日本人全体がそうである」と誤解されます。
結局、日本の生活を外から見ている人は、象徴的な現象に意識を向け、中にいる人は、現実を見ています。この視点の違いがギャップを生む一番の理由です。
ギャップから何が学べるか?
海外で語られる理想像と、実際の暮らしの間には差があります。このギャップを見ることは、より自分らしいシンプルライフを築くことに役立ちます。
たとえば、こんな学びあります。
イメージに惑わされず、自分にとってのシンプルを見つける
日本的ミニマリズムや北欧風ライフスタイルなど、メディアで紹介される理想像はイメージ先行と考えられます。
それは、すべての人の正解にはなりません。美しいイメージを追うより、普段の暮らしから、自分が心地よいと感じるポイントを見つけていくほうが有効です。
シンプルさは心の中に宿る
日本のイメージにある静寂や余白は、実際の生活ではなかなか作れません。でも、心の中に余白を作ることはできます。外的環境に頼らず、内面の静けさを育てるとよりシンプルに暮らすことができます。
本物の美意識は暮らしの中にある
海外の人が憧れるわびさびは、 これまで日本人が日常の中で自然に育んできた感性です。
たとえば、それは
・使い込まれた器に宿る美
・季節の移ろいを感じるしつらえ
・静けさの中にある豊かさ
このような感性は、ものの量ではなく、ものをどんなふうに使うか、つまり、ものとの関係性で決まります。
つまり、シンプルライフは、やみくもにものを減らすことではなく、いかにものと付き合っていくかがポイントだと言えます。
◆関連記事もどうぞ
⇒ミニマリズムに関するよくある誤解を解く。ミニマリストはモノを悪者にしている?
⇒レス・イズ・モア(Less is more)の真の意味とは?何もない部屋に住むことがミニマリストの目的ではない
⇒ミニマリストの部屋公開~最小限のモノで生活して40歳でリタイヤした男
*****
海外の日本に対するイメージと、実際の日本のギャップをシンプルライフという視点から考えてみました。
静かでシンプルな生活は、かつての日本にはあったと思います。
ただ現代は、ものがあふれ、忙しさに追われ、その姿が見えにくくなっているだけです。
海外の憧れを鏡にしながら、シンプルに暮らすことを選択すれば、かつてあった豊かさをもう一度手に入れることができるでしょう。