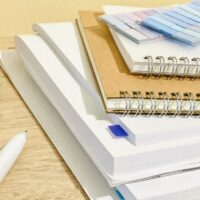ページに広告が含まれることがあります。
今回は、見えない場所にものがたまりやすい理由と、ここを見直すコツを紹介します。
テーブルの上や床の上はちゃんと片付いているのに、なんだかスッキリしないと感じたことがあるかもしれません。
その違和感の正体は、収納の奥で静かに眠っているガラクタです。たとえば、引き出しの中、収納棚の奥、玄関の靴箱や、パントリーのいちばん上の段など。
一見、目につきにくい場所にものをためこむことはよくあります。
「片付けてるのに、なんかスッキリしない」の正体
人は、ふだん目に入るところには敏感です。来客の予定があれば、テーブルの上を片付け、床に置いたものを一時的に押し入れへ。そうやって、見える場所だけを急いで整えることは、誰でもします。
私も来客がある時は目につくところだけきれいにします。
けれども、こうした行為はちゃんと片付けたとは言えません。
「とりあえず入れる」「あとで整理する」、そんな気持ちから放置された押入れの中身は、いつまでも片付けられないまま、奥まったところでガラクタ化することが多いのです。
手の届かないところに押し込まれたものたちは、目には入りません。
けれども、私たちの脳はそれを「未完了のタスク」として記憶し続けるので、気づかないうちにストレスになっています。
見えないガラクタが生活に与える影響
目につかない場所にガラクタがたまっていると、実生活にはどんな影響があるのでしょうか?
目に入らないから気にならないと思いたいところですが、実はそうでもありません。
問題1:重複買い
何がどこにどれだけあるかを把握できていないと、似たようなものを何度も買ってしまいます。歯ブラシ、乾電池、文房具、調味料、ストッキング、ハンドクリームなど、あちこちから似たようなものが出てくることはありませんか?
問題2:探しものに時間を取られる
収納スペースにものがたくさんあると、探しものをする率が上がります。
しまったはずなのにどこにあるかわからない。使いたいときにすぐ出てこない。結局、新しいものを買ってしまう。このようなことがたびたび起こると、時間だけでなく気力も奪われてしまいます。
問題3:セルフイメージの悪化
所持品をちゃんと管理できていない自分に自己嫌悪を抱きます。
「あそこに何があるかわからない」「開けるのがちょっと怖い」という気持ちは、意外と心のどこかに残っていて、じわじわとストレスになります。
さらに、はじめにも書いたように、見えないけれど気になっているものは、心の奥底でずっとひっかかっています。
片付いていない場所がひとつでもあると、脳はそのことを忘れてくれず、無意識のうちにエネルギーを使い続けてしまうのです。
表向きはスッキリしていても、収納スペースの中が散らかっていると、暮らし全体がどこか落ち着きません。
なぜ視界外ゾーンにものがたまるのか?
見えない場所にものがたまっていくのは、決して偶然ではありません。
日々の行動パターンと、ちょっとした思い込みが重なることで、ガラクタが少しずつ増えていきます。
理由1:とりあえず入れる習慣
私たちは使い終わったものをそのタイミングで手放すことはまずしません。
読み終わった本は本棚へ、買い替えて不要になったものも、とりあえず押入れなどにしまいます。
また、お客さんが来るときなど、突貫工事的にものを見えないところに入れることもよくあります。
目につく場所をきれいにするために、とりあえず引き出しや棚の中に押し込み、入れたあとはそのまま忘れてしまう。これがくり返されると、仮置きがいつのまにか常設になり、整理のタイミングを逃してしまいます。
理由2:いったん入れたものを出さない
この行動の背景にあるのは、「いつか使うかもしれない」「高かったからもったいない」といった気持ちです。
いつ使うかわからないけれど、そのうち使うかもしれないし、しまい場所もあるので、なんとなくしまっておきます。
しかし、いったん目につかない場所にしまうと、しまったこと自体を忘れます。思い出してたとしても「まだ使えるしな」と手をつけずに残してしまいます。
捨てられないモヤモヤを解消~ “もったいない”を手放す7つの心理と解決策
理由3:ためこんだもののことを考えたくない
ものが増えてくると、全体を把握できなくなり、「よくわからないけどものがいっぱい入っていそう」とざっくりした認識になります。
その結果、内容について考えたくなくなります。
何が入っているのか、自分でもよくわからない。出すのも片付けるのも手間がかかりそう。
そうなると、隠されたスペースの中を見ることすら避けてしまい、ますますものがたまりやすくなるのです。
見えない場所にガラクタをためないために
目に見えないところに、ものをためすぎないために、習慣を見直してみましょう。
なんでもかんでも入れるのをやめる
ものをしまう前に、「これは本当にここに入れるべきものか?」をしっかり考えてください。
無意識にものを押入れや棚に入れることが習慣になっているなら、「よくわからないものをとりあえず入れる場所」を一箇所だけ決めてここに入れるようにすると、家全体にものがたまりすぎません。
場所は1つだけにして、スペースは広くとりすぎないでください。
定期的に中身を見直す
月に一度ぐらい、引き出しや棚の一部を開けて中にあるものを確認しましょう。
そこに入っているものを確認するだけで、ものが増えすぎない前に、手を打つことができます。
すべてを見直す必要はないので、1回に1箇所ずつ、軽くチェックしてください。
もちろん、不用品を見つけたらすぐに処分しましょう。
むやみに収納場所を増やさない
収納スペースはむやみやたらと増やさないことをおすすめします。
収納スペースが多いと、「まだ入るからいいや」と、どんどんものを入れてしまいます。
入れる場所がなければ、目にふれるところにあふれますが、あふれるからこそ、不用品を処分する気になるのではないでしょうか?
筆子の工夫
収納スペースの奥にものがたまるのは、やはり、目視できないから忘れてしまうせいです。
今の家は収納場所は寝室のクローゼットしかないので、毎日目にふれますが、細々としたものはバンカーズボックス5つに入れているので、中にあるものを忘れがちです。
そこで私は、箱の側面に中身を書いたラベル(マスキングテープにマジックで書いただけ)を貼って、忘れないようにしています。
キッチンのキャビネット(作り付けの収納棚)の奥に入れて、ふだん目にふれないものは、時々、1段ずつ中身を全出ししてチェックしています。
こうすれば、食べ忘れているもの、ふだんあまり使わないもの、買ってそのまま忘れていたものをあぶりだすことができます。
上部のキャビネットは、奥行きが浅いので、さっと目視するだけでOK。パントリー代わりに使っている下部キャビネットの二段だけ、月に1度はしっかり調べています。
私は食品のストックはしないほうなので、そこまでものはたまりませんが。
まとめ買いが節約にならない4つの理由。むしろガラクタを増やす危険な買い方。
おわりに:見えない場所にこそ、暮らしのクセが出る
私たちが日々暮らす空間には、「気にしている場所」と「気にしていない場所」があります。
見える場所には自然と意識が向きますが、見えない場所はどうしてもそのままになりがちです。
だからこそ、視界外ゾーンにどんどんものを入れてしまうのは、シンプルライフという観点から見るとかなり危険な行動です。
「見えないところにものがびっしりあっても、外がきれいなら、べつに困らない」と思うかもしれません。
ですが、不用品をいっぱい持っていると、今使いたいものを取り出しにくくなりますし、「使っていないものをいっぱい持っている」という気持ちの負担が生じます。
時々、中身をチェックして、ものを増やしすぎないようにしましょう。