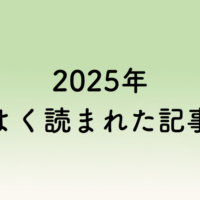ページに広告が含まれることがあります。
不要品を見極めるとき、「ときめくか?」を基準にすると、迷わず捨てられる。近藤麻理恵さんの本で、有名になった捨て方です。
でもときめきではうまく決められないという読者からお便りをいただきました。
気分や体調で答えが変わってしまう。そもそも、ときめきの感覚がよくわからない。高かったものやもらい物だと、好きかどうかより「もったいない」が先に立ってしまう……。そんな人も多いかもしれません。
この記事では、ときめき以外の基準で即決できる質問の作り方と実例を紹介します。
まずお便りを紹介します。なぎささんからいただきました。
どんな質問をしたらいいのか?
最近、断捨離を始めました。でも、迷っていることがあります。
私は、服や本、小物などを「まあ、もうここに置いてあるし、動かすのも面倒だ」と思って、使っていなくても、なかなか処分できません。そのせいで、ろくに使っていないのに場所だけ取っているものがたくさんあります。
そこで、捨てるものを判断するために、筆子さんがおすすめしている具体的なチェックリストを作ろうと考えています。
最初に、「もし引っ越すなら、これを持っていくか?」という質問を思いつきました。でもこれだと、引っ越し先の気候によって、選ぶ服が変わりますよね。
こんまりの、「ときめくかどうか」というのもやってみたんですが、その日の気分によって答えが変わってしまいます。
筆子さんは、ものを減らすとき、どんな質問を自分にしていますか?
参考にしたいので教えてください。
なぎささん、はじめまして。お便りありがとうございます。
断捨離を始められたんですね。
私はあんまり質問は考えずに、「これはもういらないから捨てよう」と、ポイっと捨てることが多いです。実際は、寄付用の箱に入れます。
自問するとしたら、「これは1年以内に使ったか?」と「これは私の人生にプラスになっているか?」という質問をよくします。
以下のように考えて、質問を作ってみてください。
質問をつくる3つのポイント
捨てるルールを自分で作るときは、次の3つを意識するといいでしょう。
1. 期限や使用頻度を入れる
「ときめくか?」で決められないなら、感情より事実に基づいた基準のほうがいいと思います。
「この1年で使ったか?」「この季節に着たか?」など、期間を区切って使ったかどうか考えるといいでしょう。長く使っていないものは今後も使う可能性が低いです。
2. 具体的な質問をする
抽象的な質問ではなく、具体的な質問にしましょう。
たとえば、「今すぐ買い直すか?」「次の旅行に持っていくか?」など、行動を伴うシーンを思い浮かべると決めやすいです。
3. 管理コストを考える
ものは置いておくだけでスペースを取るし、手入れの手間や探す時間を要します。
つまりコストがかかるので、「管理に手間がかかってもいいか?」「押入れが使いにくくなってもいいのか?」と考えてみてください。
以上の3つを組み合わせると、気分や条件に左右されにくい、自分専用のルールができると思います。
よりよい決断をする3つの方法、コンピュータのように考える(TED)
今すぐ使える質問の例
ここでは、その場で「捨てる・残す」を決めやすい、シンプルな質問の例を紹介します。必要に応じて使ってみてください。
・これがなくなったら困るか?
困らないなら残さなくても大丈夫です。同じものがいくつもあるときは、数を絞ったほうがいいですね。
・こわれたらまた買い直すか?
使えなくなったら、また同じものを買い直すなら、必要度が高いアイテムと言えます。
・この先、具体的に使う予定があるか?
「次の旅行で使う」「冬になったら着る」など、使用している状況がはっきり思い浮かぶものは残します。
・未来につれていきたいか?
自分の望む未来にこのアイテムも必要だと感じるなら、残したほうがいいでしょう。
・残す明確な理由があるか?
「なんとなく」ではなく、それを手元に置く明確な理由を言えるかどうか調べてください。はっきりとした所有する理由がないものは、ただ執着しているだけかもしれません。
・管理や手入れに時間や労力をかける価値があるか?
整理整頓や修繕など管理する負担に見合う価値があると感じるなら残し、そうでなければ手放し候補です。
判断に迷ったら
明確なルールを決めても、判断に迷うことはよくあります。
たとえば「1年使わなかったら捨てる」と決めていても、たまたま今年は使わなかっただけかもしれないと考えることもあるでしょう。
なぎささんのように、「引っ越し先がこうだったら」と「たら・れば」で考え始めてしまったら、いくらでも迷ってしまいます。
そんなときは以下のように考えてください。
決断はシンプルに
「たら・れば」で考えず、シンプルに決めましょう。
未来はわからないので、「もし、こうだったら、ああだったら」と考えだしたらきりがありません。
押入れや棚にしまいっぱなしのものは、基本的に使っておらず、必要性の低いものばかりです。そのまま、さくっと捨てても問題ないものばかりではないでしょうか?
負担が大きいものから捨てていく
それを持ち続ける負担が大きいものから手放す方法もあります。ここでいう負担は3種類あります。
・物理的負担
置き場所を取る、重くて扱いにくい、大変、掃除や手入れが面倒など。持ち続けることで部屋のスペースを圧迫したり、管理に体力が必要なものは、物理的負担が大きいです。
たとえば、かさばる大きな家具や、虫食いの心配があるカシミアのセーターなど。
・精神的負担
管理しなければと気をもむ、いつまでもそこにあるのがとても気にかかる、本当は捨てたいのに捨てられないからもどかしい。このような感情面のストレスが大きいものは捨ててしまいましょう。
・時間的負担
それがあるせいで、ほかのもの探す時間が増えている、手入れに時間がかかっているなど、時間を奪うものも、早めに手放したほうがいいです。
大事なものを先に選ぶ
捨てる・捨てないですごく迷ってしまうなら、先に、どうしてもはずせないものを選び、残りを処分するという方法もあります。
この方法は、完璧主義的傾向のある人に特におすすめです。完璧主義の人は、「間違った選択をしたくない」という気持ちが強いので、必要以上に迷います。
先に必要なものを選べば、大事なものを捨てて後悔する恐れがなくなります。
このやり方は、思い出のあるアイテムや、数が多すぎるものに有効です。
それでは、なぎささんの断捨離がうまくいくことを祈っています。がんばってください。
捨てる・捨てないを決める:関連記事もどうぞ
捨てるものがわからない時に使ってほしい、物の価値を見極める10の質問リスト。
捨てる・捨てないで迷ったときの3つの考え方~しっかり自分に向き合えば、決められる。
こんまりの「ときめき」がよくわからないあなたへ。捨てる物を決める15の質問
*****
読者の質問に回答しました。
断捨離をするとき、多くの人は、「捨ててしまったあとに起きるかもしれない困ったこと」を考えるので、全然使っていないものなのに、捨てる決断がなかなかできません。
暗い未来を先回りして考える人は、捨てるからこそ得られるものに目を向けるといいでしょう。
不安をベースに決めるのではなく、希望や可能性を見ながら決めてください。
実際、不要品を手放せば、スペースや身軽さ、時間は確実に手に入ります。断捨離をして、生活に余裕をつくれば、新しいものとの出会いもありますよ。