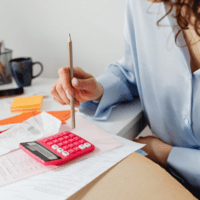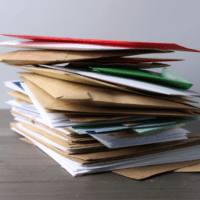ページに広告が含まれることがあります。
読者の片付け相談に回答します。
今回お便りをくださった方はお子さんの作品を捨てるのに苦労しています。
まずお便りを紹介しますね。よつばママさんからいただきました。
ミニマリストになりたいのに
いつもブログを楽しく読んでいます。
私は40代後半の専業主婦で、子どもが4人います。自分でもADHD傾向があると感じていて、家事や片づけが本当に苦手です。
ミニマリストのようなすっきりした暮らしにあこがれているのですが、実際にやろうとすると、どうしてもモノへの執着があって手放せません。
たとえば、子どもが学校で描いた絵や作文など、捨てたって困らないと頭ではわかっていても、罪悪感があって処分できないのです。
また、がんばって片づけても、ただモノの置き場所が変わっただけで、結局何も減っていないような気がします。やる気もすぐになくなってしまいます。
こういう状態でも、シンプルライフを目指すことはできるでしょうか?
なにかアドバイスがあれば、お聞きしたいです。
よつばママさん、こんにちは。お便りありがとうございます。
お子さんが4人もいると、子育ても家事も大変ですよね。
そんな中、暮らしをよくしようと努力されていて本当にすごいと思います。
たしかに、子どもの作品ってなかなか捨てられないですよね。
わたし自身も娘が小さいころは、描いた絵や工作をずっと取っておいた経験があります。
今でも娘がトゥースフェアリー(歯の妖精)に書いた手紙は取ってありますよ。
幼い頃の手紙は、文字がかわいですよね。
子どもの作品を特に捨てにくいのは、ちゃんと理由があります。
その気持ちとどう向き合えばいいのか、そして、子どもの作品を無理なく手放す工夫について、わたしの経験も交えてお話ししていきますね。
子どもの作品が捨てられないのは自然なこと
子どもの作品を捨てにくいと思うのはあたりまえのことなので、捨てられない自分を責めるのをやめましょう。
この悩みは、多くの方が抱えています。
小さい子どもは、日々いろんな作品を家で作り、幼稚園や学校でも作って持ち帰ってきます。
私の娘も、クラフトが好きだったので、毎日、裏紙に絵を何枚も描いて、しかもそれを壁にベタベタと貼っていました。
お絵描き、工作、作文、自由研究、塗り絵。どれも子どもの成長が感じられて、つい「これは残しておきたい」と思ってしまうでしょう。
それは片づけが苦手だからそうなるのではなく、親としての自然な反応です。
子どもの作品には、そのときの思い出が詰まっていますし、自分の育児を肯定したい気持ちも重なっています。
「これを捨てたら、愛情がなかったことになるんじゃないか」「子どものことを大切にしなかったことにならないか」と不安になることもあるかもしれません。
だから、まずは「捨てられない私ってダメだな」と思わないことが重要です。
それでも手放すべき理由
それでも、ある程度のところで見切りをつけて、手放す必要があります。
現実問題として、作品はどんどん増えていきます。4人のお子さんがいれば、量も4倍です。限られた収納スペースにずっと保管しておくことは難しいし、数が多すぎると、せっかくの作品をゆっくり見ることすらできなくなります。
保管されているものが多いと、物理的にも心の中のスペースも、どんどん奪われてしまいます。
視覚的な情報が増えるため、脳がその情報を処理しようとして疲れますし、見るたびに、「片づけがちゃんとできていない」という気持ちがわいてきて、余計にしんどくなります。
ミニマルライフは、ものを減らすこと以上に、気持ちの負担を軽くしていく生き方だと私は思っています。
作品をすべてとっておくことよりも、子どもとの思い出だけを残して、大半は手放すことにしたほうが、心が安定し、暮らしも快適になります。
子どもの作品を手放す3つの工夫
手近なところから、作品を取り出して、もういらないと思うものは捨ててください。
基本的な方針としては以下の3つをおすすめします。
1. 写真に撮って、デジタル保存
今はスマホで簡単に写真が撮れますし、クラウドストーレージやアプリを使えば、まとめて保存することもできます。
写真で残しておけば、思い出を失ったとは感じないでしょう。
わたしは、写真は全部、Googleフォトに入れていますが、「art」で検索すると、娘の作品が写った写真が全部出てきます。
たとえばこんな写真です。

似たようなサービスはほかの写真アプリにもあると思うので、わざわざアルバムを作らなくても、あとで簡単にテーマを絞って見られます。
こうすれば、見返すのは簡単だし、必要なら印刷してフォトブックを作ることもできます。
思い出を大切にしたいからといって、実物をずっと取っておく必要はないんです。ぜひ、デジタル技術を活用してください。
2. 厳選ルールを決める
捨てる・捨てないを決めるとき、どれも「そこそこ大事」に見えてしまって選べないかもしれません。そこで、あらかじめ自分でルールを決めておくといいでしょう。
たとえば、
・1学期に1作品だけ残す
・子ども1人につき、最大10作品までにする
・「初めて」と名のつくものだけ残す
以上はわりと作品を絞り込む感じのルールですが、もっとゆるくてもかまいません。
自分なりの残す基準を作って、それに従って断捨離すれば、手放しやすいでしょう。
子どもと一緒に選ぶのもひとつの方法です。「この中で一番気に入ってるの、どれ?」と聞いてみると、案外あっさり「これいらない」と言われることもありますよ。
実際、今、26歳の私の娘は自分の作品にまったく愛着を持っていません。
3. 一時保管ボックスを使う
すぐに判断できないときは、いったん保留にするのもいいでしょう。
作品専用のボックスを用意して、そこに一時的に入れておきます。
定期的に見直して、「まだ残しておきたいか?」と自分に聞いてみてください。
時間が経つと子どももそれに応じて大きくなっているから、「あ、これはもういいかな」と自然に取捨選択できるでしょう。
感情がまだ強く動いているうちは、無理に手放さなくてもいいのです。
片づけ疲れへの対処法
片づけで疲れないように、少しずつ断捨離してください。
片づけは、ものを「いる・いらない」と判断する小さな決断の連続です。
ADHD傾向がある人は、こうした決断を繰り返す作業が苦手で、疲れやすいと言われています。
疲れるとやる気がなくなり、「やっぱりわたしはダメだ」と自己否定のループにはまりがちです。
まずは、全部一気にやろうと思わないこと。
「今日は子どもの作品を3枚だけ見直す」というやり方でもOKです。
もし、減らすことが難しければ、見ないようにするだけでも、効果があります。たとえば、作品をまとめて箱に入れてクローゼットの上段にしまうだけでも、視界がすっきりして心がラクになることがあります。
お便りにあった「がんばって片づけても、ただものが移動しているだけ」と思ったとしても大丈夫です。
整理すれば、視覚的ノイズが減ります。
ミニマルな暮らしは完璧じゃなくていい
最後に、完璧主義にならないことをおすすめします。
「筆子さんって、すごくストイックに片づけしてるんでしょ?」と思われがちですが、私も全部のものを完璧に管理できているわけではありません。
娘が小さかったころ作った作品は、去年の5月、引っ越しをしたときに、そのままここに置いておくという決断をしたものもたくさんあります。
ミニマリストの暮らしは、完璧な空間を作ることではありません。
・自分が大切にしたいものを、自分で選ぶこと
・生活が少しでもラクになるように、工夫していくこと
こうやって、少しずつ整えていく生活がミニマルライフだと思います。
今回紹介した工夫を取り入れれば、ADHD傾向があっても、シンプルな暮らしを目指すことはできますよ。
それでは、よつばママさんの片づけが少しでも前に進むことを祈っています。
どうぞ、お元気でお過ごしください。
レス・イズ・モア(Less is more)の真の意味とは?何もない部屋に住むことがミニマリストの目的ではない
子どもの作品の整理・関連記事もどうぞ
たった1つだけ考え方を変えれば、子どもの作品、図画、工作は簡単に捨てられる
狭い賃貸マンションで子どもが3人いて、ものが多くてスッキリ暮らせない。ストレスでいっぱいです←質問の回答。
春休みがチャンス。子どもの作品を処分する方法。保存するものはこうして選ぶ
さっさと捨てたほうがいい理由:古い作品を残すメリットとデメリット
******
子どもの作品を捨てるのがつらいのは、それだけ家族を大切に思っている証拠です。
完璧を目指さず、自分に合った方法で少しずつ手放していけばいいのです。
写真に撮る、数を決める、保留にする。無理しなくてもできる方法を選んでください。
無理をするとあとでリバウンドします。
片づけは、自分や家族の暮らしを整えていくプロセスです。
焦らず、自分のペースで進めていきましょう。
お知らせ:エッセオンラインの新記事
エッセオンラインに新しい記事がアップされました。今回は、トイレになくてもよさそうなものの話です。
⇒50代・トイレに「なくても困らなかった」もの。当たり前を手放したら暮らしがラクに | ESSEonline(エッセ オンライン)
読んでみてください。