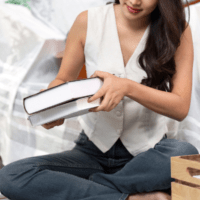ページに広告が含まれることがあります。
断捨離を始めると、家の中に無料でもらったものがたくさんあることに気づきます。
1円も払っていないおまけなのに、なぜか捨てにくい。どうしてそんなことが起こるのかこの記事で理由を説明します。
スーパーの試供品、展示会でもらったパンフレット、通販の箱に入っていたおまけ。自分からお金を出して買うことはないのに、つい受け取ってしまい、なかなか捨てられずにためこんでいること、よくありますよね?
支払ったお金はゼロなのに、処分しようとすると、妙な罪悪感やもったいなさを感じます。
なぜ、無料のおまけはこんなにも捨てにくいのでしょうか? その理由を、心理学や文化的な背景から5つにわけて解説します。
私が言いたいことは一つだけ。おまけは捨てにくいので、もらわないことが一番です。
1.エンダウメント効果:所有した途端に価値が上がる
無料でもらった品物でも、手に入れた途端に、自分の中で価値が上がります。
これは、心理学で「エンダウメント効果(授かり効果)」と呼ばれる現象です。
人はいったん所有したものを、客観的な価値以上に高く見積もってしまいます。
この心理を示す、マグカップを使った有名な実験があります。
マグカップをもらった学生が「これをいくらで売るか」と問われて答えた金額は、マグカップを持っていない学生が「買ってもいい」と考えた金額よりもはるかに高いものでした。
エンダウメント効果が起きる理由は、何かを所有した瞬間に「これは私のもの」という感覚が生まれるせいだと言われています。
人は自分と関係のあるものを高く評価する傾向があり、それは、所持品に対しても同じです。
だから、たとえお金を出して手に入れていなくても、自分のものになった以上、大事なものに思えてしまうのです。
授かり効果のせいで捨てられない物を捨てられるようになる考え方
2.返報性の原理:もらったから粗末にできない
無料のおまけを捨てにくい2つ目の理由は、「返報性の原理」と呼ばれる心理です。
これは、人から何かをもらったら、お返しをしなければならないと感じる心理です。本来はいい人間関係を築くために役立つ心理ですが、販促品をもらっても同じように感じます。
街でもらうポケットティッシュ、レジ袋の底に入っているおまけなど、くれた相手の顔がわからなくても、「せっかくもらったのだから、粗末にしてはいけない」と思います。
粗品をもらったとき、実際に相手にお返しすることはありませんが、捨てずに取っておくこと自体がお返し代わりになると感じることがあります。
「もらったのにすぐ処分するのは悪い」と感じ、その罪悪感を和らげるために保管します。
3.希少性効果:限定・非売品に弱い
おまけの中には、手に入りにくいものもあります。こうしたおまけには、希少性効果と呼ばれる心理が働きます。
珍しくて、手に入りにくいものほど、価値が高く感じられる心理です。
普段なら必要だと感じない品物でも、「非売品」「先着○名様」「今だけ」といった言葉がつくと、特別なものになり、価値のあるものに思えます。
たとえば、コンビニのキャンペーンでもらうグッズや、コンサート会場で配布される限定品など。使うことはなくても、「もう二度と手に入らない」という気持ちがあるので、大事な記念品のように扱ってしまいます。
企業はこの心理を利用して、限定キャンペーンや先着特典を設け、人々の関心を引きつけます。
限定品という言葉につられて買ってしまわないために:要注意のキャッチフレーズ、その2
4.人からもらったものには特別な意味がつく
無料のおまけでも、人から受け取ると、単なるもの以上の重みが加わります。
この現象には、心理学でいう「社会的意味づけ」が関係しています。
「誰かからもらった」という事実ややり取りの場面が記憶に残り、それがもらったものの価値に上乗せされます。
街頭で見知らぬ人からポケットティッシュを渡された場合でも、「駅前でもらった」「あのとき受け取った」という場面と結びつきます。
相手が赤の他人であっても、「人から与えられた」という事実が無意識のうちに特別感を生みます。笑顔で渡されたり、丁寧な言葉をかけられたりしていると、さらにものに対して好意的な印象が加わることもあります。
「人からもらったものを粗末にしてはいけない」という感覚は、多くの人に共通しています。
ただ、日本では贈答文化や「もったいない」という価値観があるので、この意識が特に強いと思います。そのため、親しい人からもらっていないものでも、処分するのは簡単ではありません。
人とのやりとりが結びついたおまけは、こんなふうにして特別なものとなり、捨てにくいのです。
5.もったいない文化:ゼロ円でも価値を感じる心理
無料のおまけが捨てにくい背景には、「もったいない」という文化的価値観もあります。
「もったいない」という気持ちは、本来は資源を大切に使い切るための考え方で、食べ物や日用品を無駄にしない知恵として根づいてきました。
しかし多くの人は、無料でもらったおまけに対しても、「捨てるのはもったいない」と感じます。
「使えるものだから」と考え、今後の必要性より、「もったいない」という気持ちを重要視します。
新品のペンがたくさんあっても、まだ使える鉛筆やペンを捨てるのは惜しい、と感じる人は多いでしょう。私もサインペンを断捨離するときは、いちいち書いてみて、色が少しでも出るなら捨てない方です。
「もったいない」という言葉には、ただの節約以上の意味が込められています。
明治時代以降、この言葉は道徳教育の中でも使われてきました。戦後の、ものが不足していた時代には、ものを最後まで使い切ることがよいことだとされ、多くの人の価値観に根づきました。
その考え方は今も残っていて、たとえ無料でもらった景品であっても、「粗末に扱うのはよくない」と感じる人が多いと思います。
「もったいない」という言葉は、今では海外でも、環境問題やエコの象徴として紹介されることがあります。
日本人にとって「もったいない」は、ものを大切にするだけでなく、資源や環境を守る意識ともつながっています。
こうした感覚があるからこそ、無料で手に入れたおまけであっても「無駄にしてはいけない」と感じ、処分をためらいやすくなるのです。
◆おまけ関連記事もどうぞ
⇒断捨離の天敵、無料サンプルや値引き品の誘惑に打ち勝つ5つの方法
まとめ:おまけをためない工夫を
無料なのにおまけや粗品が捨てにくい背景には、心理的な働きや文化的背景が関わっていることを紹介しました。
おまけは捨てにくいので、シンプルに暮らすなら、最初から家に入れないほうがいいと思います。
そのために、不要なおまけは断りましょう。
自分で取ってくる場合は、必要な分以上は取らないようにします。
受け取る場合は、「いりません」「大丈夫です」と断ってください。
断り慣れていないと最初は抵抗があるかもしれません。でも何回か断っているうちに、それが普通になります。
必要のないものを受け取らなければ、あとで管理や処分に悩むこともありません。
すでに家の中におまけがたくさんある場合は少しずつ手放してください。
1日15分ぐらい、おまけをしまってある場所を片付けるといいでしょう。
手に入れるときお金を払っていなくても、ものはものです。
しまうスペースが必要だし、管理の手間も発生します。
おまけがたくさんあると、本当に必要なものを取り出しにくくなります。
不要なおまけを手放して、今後はできるだけ受け取らないようにすると、日々のものの管理がラクになります。