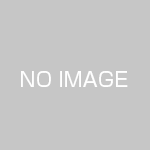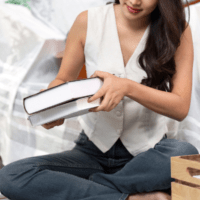ページに広告が含まれることがあります。
日々の暮らしにむなしさを感じている人に見ていただきたいTEDトークを紹介します。
タイトルは、Why We Need to Know Our Lives Matter(なぜ私たちは、自分の人生が重要だと知るべきなのか?)
ジャーナリストのJennifer Wallace(ジェニファー・ウォレス)さんの講演です。
人は、自分の存在が誰かの役に立っている、意味があると感じられるときに、生きる力がわいてきます。
その感覚を大事にし、互いに思い出させることが個人にも社会にも必要だ、とウォレスさんは伝えます。
自分は価値がある
収録は2025年の4月、動画の長さは12分30秒、英語ほか複数の字幕があります。動画のあとに抄訳を書きます。
◆TEDの説明はこちら⇒TEDの記事のまとめ(1)ミニマリスト的生き方の参考に
◆トランスクリプトはこちら⇒Jennifer Wallace: Why we need to know our lives matter | TED Talk
トークで繰り返し出てくる mattering(マタリング) とは、「自分は誰かにとって意味のある存在だ」と感じられることです。
自分の存在が必要とされ、役に立っていると実感できる状態に近い概念です。
ジェニファーさんはとてもゆっくりしゃべっているので英語は聞き取りやすいです。
命を救う仕事でもむなしい
世界で最も意義のある仕事と聞いて思い浮かべるものに、消防士がありますよね。
多くの人は危険から逃げるのに、彼らはまっすぐ危険に飛び込み、命をかけて人びとを救います。
消防士の仕事が世界に大きな影響を与えているのは明らかです。
少なくとも私はずっとそう思っていました。グレッグという消防士に出会うまでは。
彼は、消防士でも、自分の仕事の意義を感じられなくなることがあると話しました。
救助した人のその後がわからない
グレッグが新人のとき、大きな交通事故現場に仲間と出向きました。
女性が車内に閉じ込められて、足がねじれた鉄の下敷きになっていました。
グレッグは訓練通りに動きました。隙間を探して中に入り、ガラスの破片から守るために、女性に自分の重い防火服をかけました。
救助作業の間、ちゃんとそばにいると約束し、実際に彼女を救出しました。
この話で私の心に残ったのはその後のことです。
この出来事のあと、グレッグが、その後どうなったのかを知ることはありませんでした。
あの女性は助かったのか? また歩けるようになったのか? あの夜の自分たちの働きに何か意味があったのか?
消防士たちは、救助したその後のことは、ほとんど知らされないと知って私は驚きました。
結末がわからないせいで、時間が経つにつれ、士気をそがれ、燃え尽きたり、シニシズム(物事を皮肉っぽく、疑って見る姿勢)に陥ったりします。
大切な仕事をするだけでは足りない
ずいぶん経ってグレッグが消防署長になったとき、どんな救助にどんな結果があったのかを記録するシステムを作りました。
消防士たちに、自分たちの行動が誰かの命を救ったり、苦しみを和らげたりしたと知らせたかったからです。
グレッグは大事なことを知っていました:大切な仕事をするだけでは足りない。自分の仕事が違いを生んでいると私たちは知る必要がある。
自分の存在が意味を持つと実感することが必要です。
多くの人が自分の価値を感じられない
ジャーナリストとして、過去6年間、世界中で何百人もの人に話を聞き、ある質問をしてきました。
「あなたは、自分の存在や行動が誰かにとって意味があると感じますか?」
あまりに多くの人が、「いいえ」と答えました。
ある医師は、保険会社が患者に必要な治療を認めなくなり、自分には何もできない、無力だと感じるようになったと言いました。
ある大学生は、成績がよくて、体重が軽いときだけ価値があると感じると言いました。
ある高齢の男性は、年を取ることで一番つらいのは、誰も自分を頼らなくなることだと言いました。
価値ある存在だと知ることが大切
こうした話や科学的研究から、はっきりと分かったことがあります。
生き生きと人生を送るには、「自分は価値ある存在だ」と感じることが必要だということです。
これは、「自分は認められている」そして「自分が社会に価値を付け加える機会がある」と感じることです。
自分は重要な存在だと感じられれば、人は全力でその場に向き合います。人とつながりたい、関わりたい、貢献したいと思います。
反対に「自分は重要じゃない」と感じると、人は心を閉ざします。
その苦しみをまぎらわすために、薬物や自傷行為に走る人もいます。
ある人は怒りを外に向けます。ロードレイジ(運転中にすごく怒ること)、ネット上の攻撃、政治的な過激さ――これらはすべて、「自分は意味のある存在なんだ」と必死に訴えています。
状況は、これからさらに悪化するでしょう。
AIの登場で、自分はこういう人だという感覚や目的を与えてくれていた仕事がなくなっていくので、さらに多くの人が自分の存在意義を感じられなくなります。
必要なのは、AIに置いていかれないようにすることだけではありません。
人間であることの意味や価値を感じ、ほかの人も価値ある存在だと伝え合っていかねばなりません。
職場でも自分の価値を感じたい
暮らしたり働いたりする場所は、自分には価値がないかもしれないという不安を強めることもあれば、和らげることもあります。
ウィスコンシン州フィリップスにある工場では、各作業台に写真がついたカードが置かれています。
カードには、自分たちが作っている部品が最終的な製品のどこに使われるのか、誰の役に立つのか書かれていました。
さらに、その製品を使うことになる人の写真と物語も添えられていました。
カードのおかげで、労働者たちは、自分たちはただ部品を組み立てているだけではない。意味のあるものを作っていると感じることができます。
職場で「自分は必要な存在だ」と感じることは、感傷的な、「あったほうがいいもの」ではありません。
実際に、ビジネスに役立ちます。
自分は重要だと感じられる社員は、より一生懸命働き、忠誠心を持ち、より多くのエネルギーを仕事に注ぎます。
価値を与える機会も必要
自分が重要な存在だと感じるだけでは、自分の価値を感じられません。
誰かの役に立てる、価値を生み出せる機会がないと、自分の存在意義を感じられないのです。
私のリサーチから、そうできる具体的な方法が見つかりました。
それは、世界やコミュニティ、身近な場所で、今、必要とされていることを見つけて、 自分の持っている力、強みや知識、経験や才能を使って応えることです。
ボストン郊外に住むジュリーという女性の話を紹介します。
ジュリーは2年間、フルタイムで母親の介護をしていました。母が亡くなったあと、ジュリーは支えや目的をなくした気がしました。
しかし彼女は悲しみの中に閉じこもらず、自分が役に立てる道を外の世界に探し始めました。
そしてコミュニティで、自分が求められている場が2つあると気づきました。
1つは、ジュリーのように大切な人を亡くし、遺品をどうすればいいか分からず苦しんでいる家族。
もう1つは、火事やホームレス状態から再出発しようとしている家族。
ジュリーはこの2つをつなぎました。友人と一緒に、まだまだ使える家庭用品を集め、必要とする人たちに届け始めたのです。
この小さな思いやりあふれる行動は、ジュリー自身を含め、何千もの人生を変えることになりました。
いつでも役立つ存在になれる
この会場にいる人は皆、生きる過程で痛みを伴う変化を経験します。
大切な人を失うこと、病気、子どもが巣立って家を離れること、あるいは退職。
こうした変化を体験すると、「自分はまだ誰かに必要とされているのか?」と感じます。
しかし、ジュリーのように、どんな人にも再び役に立つ存在になる機会や責任があります。
それは小さなことから始めることができます。
近所の人の様子を気にかける、いつも親切にしてくれる同僚に「ありがとう」と言葉にして伝える。
「自分には価値がある」と再び感じる一番簡単な方法は、誰かに「あなたには価値がある」と伝えることです。
頼られすぎてもつらい
ここで、こう思う人もいるかもしれません。
「私の問題は、必要とされていないことではなく、必要とされすぎて苦しくなることなんです」と。
これもまた、「価値の危機(crisis of mattering)」と言えます。
本当の意味で価値ある存在でいることは、自分を限界まで犠牲にすることではありません。
バランスが大切です。自分のニーズと他者のニーズのあいだで、調和を取るべきです。
最適なバランスを見つける
私は何年ものあいだ、ちょうどいいバランスを見つけられずにいました。でも、マヨ・クリニックが行った研究を読み、その方法がわかりました。
その研究では、レジリエンス(心の回復力)を高めるために、ごくシンプルなことが試されていました。
対象となったのは、医療従事者であり、同時に母親でもある女性たちです。
彼女たちは週に1時間集まり、自身が抱えている苦労を語り合い、互いに支え合いました。
3か月後、参加者のメンタルヘルスと幸福度が明らかに改善しました。
ストレスホルモンであるコルチゾールの数値が下がり、皆、前よりもよい親になれた気がすると報告しました。
ケアをする側にいる人たちが、しっかり支えられていると、強くなれます。
その強さは、子どもたちへ広がっていきます。
何十年にもわたるレジリエンスの研究によれば、子どものレジリエンスは、その周りにいる大人のレジリエンスから生まれ、大人のレジリエンスは、人と深く支え合うことで強くなります。
ケアする立場にいる人は、「まず自分の酸素マスクをつけなさい」と言われます。
でも、この研究から私はそれ以上のことを学びました。
友人こそが、酸素なのです。
私たちは、1人か2人、3人の、自分をよく知っていて、苦しんでいるときに気づいてくれ、酸素マスクをつけてくれる存在が必要です。
これは、今の忙しすぎる社会で一般的とされているサポートのレベルとは、まったく違うレベルです。
助けを求めることは相手のためにもなる
でも私は今、こう考えています。
助けを求めないということは、必要な支えを自分から遠ざけているだけではありません。
助けようとしてくれる友人から、役に立てる機会や、自分は必要とされているという感覚、つまり「自分には価値がある」と感じる機会を奪っています。
次に助けを求めることをためらったら、こう考えてください。
助けを求めることは弱いことではなく、やさしいことなのだと。
人とつながると価値を感じられる
「自分は価値ある存在だ」と感じることは、個人的な経験ですが、人とのつながりの中で生まれるものでもあります。
つながることは、分断されたこの世界を結びつけることに役立ちます。
オランダのスーパーマーケット、Jumbo」は、スロー・チェックアウトレーンというレジを設けています。
このレジでは、店員が高齢者などとゆっくり会話をするんです。
孤独を減らすこの工夫は、すでに200店舗近くで導入されています。
新しい場所をつくる必要はありません。今すでにある場所で、互いの価値を大事にする意識を持てばいいのです。
自分や他の人が価値ある存在なんだと考えるようになると、もう別の見方はできません。
やがてそれは、自分の責任のように感じられます。
私自身、そうでした。家族や友人、同僚、そして街で出会う見知らぬ人に対しても、接し方が変わりました。
お互いの価値を認め合うことが必要です。それは、健全な社会を維持する接着剤のようなものです。
私たちは皆、心の奥底で、同じことを求めています。
自分という存在と自分のしていることが、この世界に何かしらの違いをもたらしていることを知りたいのです。
自分の人生も、そして存在そのものも、価値があると知りたいのです。
生きる意味に関するほかのTEDトーク
幸せになるだけが人生じゃない。生きる意味が見つかる4つの柱(TED)
成功すると幸せになるのではなく、幸せだから成功する~ショーン・エイカー(TED)
仕事の失敗でいちいち落ち込まない方法。親切で、優しい成功哲学(TED)
誰かの役に立てたとき、人は生きる力を取り戻す
生きていると、「これって何の意味があるんだろう」と感じる瞬間があります。
ただ忙しいだけの日々、大きな仕事が終わって心にぽっかり穴があいたとき、うまく人と関われなかったときなどに。
そんなとき、誰かの役に立てたと思える瞬間があると、大きく落ち込みません。
私たちは「もっと成果を出さなければ」「ちゃんとしなければ」と大きな成果を求めがちです。
でも、本当に人を支えてくれるのは、評価や肩書きではなく、自分の存在が意味を持っているという実感です。
誰かにとって必要な存在だと感じられれば、孤独やむなしさは少しやわらぎます。
役に立てる場所は、遠くではなく、すぐそばにあります。たとえば:
・スーパーで高い棚の商品を取ってあげたら「助かりました」と言われた
・具合の悪そうな同僚の仕事を引き受けたら感謝された
・友人の悩みを聞いたら「聞いてもらえてよかった」と言われた
どれも特別な出来事ではありません。でも、「あ、私の存在が誰かの今日をちょっとよくしたかもしれない」と感じられます。
もし今、むなしいなら、目の前の誰かに手を差し伸べてみてください。
自分にも誰かを支える力があると気づいたとき、人はまた明日もがんばろうと思うものです。