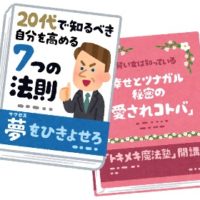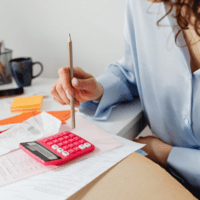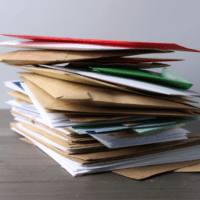ページに広告が含まれることがあります。
ものを少し減らしてスッキリ暮らしたい。そう思って片付けを始めても、ものを捨てるのはなかなかむずかしいもの。
いざ手放そうとするといろいろな思いがよぎります。
今回は、その「思い」、つまり、捨てたいのに捨てられないときの心理を9つ紹介します。
対処法も書くので、自分はどのタイプなのか、考えてみてください。自分がひっかかるポイントがわかれば、もう少し、ラクに捨てられるかもしれません。
1.ノスタルジー重視型
思い出と結びついたものがたくさんあり、なかなか手放せないタイプです。
たとえば、旅先で買った置物や、子どもが幼い頃に描いた絵、若いころ使っていた腕時計など、「見れば思い出がよみがえるから」とものをたくさん残している人。
私は思い出を大事にすることは否定しません。ただ、ものが増えすぎて、今の暮らしを圧迫しているなら、少し見直したほうが、生活しやすくなります。
思い出とものを切り離す
「思い出=もの」と思い込まず、思い出は思い出として、自分の心の中に残っていると考えましょう。
実際、私は、思い出の品らしきものはほとんど持っていませんが、毎日のように過去のできごとを思い出します。
捨てられない思い出品を手放す秘訣~保有効果の影響を最小限にする。
どうしても迷うものは、写真に撮ってから手放せば、思い出すきっかけは残ります。
2.念のため型
「いつか必要になるかもしれない」「また使う時が来るかも」「捨てたらあとで困るかも」。こんなふうに思って、使っていないものを保管し続けるタイプです。
この心理があるとき、予備のタオル、空き瓶、買い替えて不要になった電化製品、昔の仕事の資料、サイズが合わなくなった服などがたまります。
なくても大丈夫
いつか、何かのときに使えるものを持っていても、それが役立つ日が来る可能性は限りなく低いです。
あなたの人生に役立つものなら、今、使っていると思います。
それに必要になったときには、改めて手に入れることも難しくありません。
今後もものは生産され続け、店に並び続けます。
3.もったいない型
「壊れてないのに捨てるなんて」「高かったから捨てにくい」「まだまだ使える」。そんな思いから不用品を手放せないタイプです。
使えるかどうかを重視しすぎて、実際には使っていないのにとっておく選択をしてしまいます。
このタイプの方は、エコ意識や節約意識が高いのかもしれません。
今の自分が必要なのか?
自宅は店舗や倉庫ではありません。それが使えるかどうかではなく、今の自分が実際に使っているか? もしくは、近い将来使う見込みがあるかどうかを基準に考えましょう。
必要な人に譲ったり、寄付したりすると、「もったいない気持ち」にうまく折り合いをつけられるかもしれません。
4.義理人情型
人からもらったものを、「捨てたら申し訳ない」「相手の気持ちを無下にしたくない」と思って手放せないタイプです。
たとえば、誕生日や退職祝いでもらった品、結婚祝い、お土産、各種記念品、年賀状、誕生日カードなど。「せっかくもらったのに」という気持ちが強く、使っていなくても、ずっとしまいっぱなしでも捨てません。
相手の気持ちはもう届いている
プレゼントは、くれた人の「あなたに贈りたい」という気持ちが伝わった時点で完結したと考えましょう。
使わないまま置いておくより、感謝の気持ちを持って手放すほうが、贈り主にとっても、自分にとってもいい選択になると思いませんか?
義理母の手作りのプレゼントを受け取りたくないけど、断って悲しませたくない。どうしたらいいの?
5.先延ばし型
片付ける気持ちはあるけれど、「今日は疲れているから」「週末にやろう」などと、片付けを先延ばしにしてしまうタイプです。
このようなとき、「今は捨てたくない」という気持ちが背後にあります。
週末が来ても、やる気が出ない、決断するのが面倒、考えるのが億劫などの理由で、やはり手がつかず、ずっとものだらけの部屋で過ごします。
1つだけ捨てる
片付けは気合で一気に行うものではありません。毎日、少しずつ捨ててきれいにする方向にシフトしましょう。
紙袋1つ、ハンガー1本、紙切れ1枚など、超ミニマムな単位でいいので、今日、何か1つだけ捨ててください。
明日になったら同じことをします。明後日もそうです。
6.自己保存型
「これは自分の歴史」「努力の証」「この服を着ていた頃の私が好きだった」。そんなふうに、ものに自分自身の一部、もしくは大半を重ねているタイプです。
ものイコール自分なので、何かを捨てるのは、自分を否定するようで、つらく感じてしまいます。
自分の価値は、ものに宿らない
今の自分を形作っているのは、これまでのすべてのできごとであり、押入れの中にたまっているものではありません。
過去の自分ががんばった証は、ものではなく記憶やスキルに残っています。
「あの頃の自分がいたから、今の自分がいる」と考えましょう。そうすれば、手放すことは、過去の自分を否定することではなく、その経験をちゃんと認めて前に進むことになります。
7.優柔不断型
「これはまだ使えるし…でも、使ってないし…どうしよう」と迷ってばかりで、結局何も捨てられないタイプです。
判断に時間がかかる、決めるのが怖い、選ぶのが苦手という人もここに当てはまります。
使っていない時点で選択からはずれている
必要なものは、毎日使っているだろうし、今、この瞬間使っていなくても、使う予定が明確なもの(たとえばパスポート)は、そもそも捨てようとは思いません。
捨てるかどうか迷っているなら、すでに、自分が選んでいない可能性大です。
迷いがちな人は、大事なものを最初に取ってから、残りを捨てるといいでしょう。
8.コレクター型
「揃えるのが楽しい」「全作品手に入れておきたい」「コンプリートを崩したくない」と、コレクションすることに価値を置き、手放せないタイプです。
このような人の家には、過去の趣味で集めたものや、シリーズでそろえたくて買ったグッズ、限定アイテムなどがたくさんあります。
好きなものを厳選して持つ
コレクションをするには、時間、気持ち、スペースに余裕が必要です。
そうしたリソースをこれからも、そのコレクションに注ぐ覚悟があるなら、持ち続けてもいいでしょう。
そうでないなら、厳選して持つことをおすすめします。
すべてを持たなくても、とびきり好きな3つだけを残してみてください。満足感は変わらないか、むしろアップします。
9.気遣い型
「これを捨てたら親に怒られそう」「夫が残してって言いそう」など、他人の意見に左右されてしまうタイプです。
たいていの場合、実際にはまだ何も言われていないうちから、気遣っています。
このような人は、自分のものなのに、自分で判断できないまま持ち続けるストレスが続きます。
試しに1つ捨ててみる
他人の目を気にして、自分のものを捨てられない人におすすめなのは、何でもいいから1つ捨ててみることです。
そして、実際に何が起きるか観察しましょう。
私は、特に何も起こらないと推測します。なぜなら、それはあなたのものだから。
「何か言われそう」という恐れは、自分が頭の中だけで勝手に作っている恐怖です。
昨日と違う選択をする
捨てたいのに捨てられない心理を9つのタイプに分けて紹介しました。
どれも、人として自然な感情だと思います。
ただ、自然な感情だから優先してもいいというわけではありません。
そんなことをしていたら、ものはいつまで立っても減りません。
いつまでも同じ場所で立ち止まらず、きのうと違う選択をしてみましょう。
思い出を手放すのがイヤなら、写真に残す、小さなスペースから片付けてみるなど、負担があまりない片付けをしてみてはどうでしょうか?
そうすることで突破口が開きます。