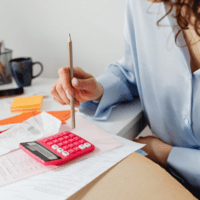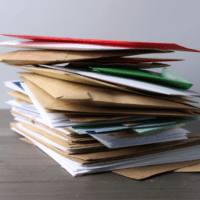ページに広告が含まれることがあります。
誰かのひと言やちょっとした態度に、いらだったり、違和感を感じることってありますよね?
人の言動を必要以上に気にして、ささいなことを「自分のせいかも」と個人的に受け取ってしまうことはよくあります。
そんなとき、ストレスを抱えなくて済むのに役立つ、Why You Take Things Personally—and How to Stop(なぜ私たちは物事を個人的に受け取ってしまうのか、そしてその対処法)というトークを紹介します。
スピーカーは、コミュニケーションとマネジメントの専門家であるHeath Butler(ヒース・バトラー)さんです。
個人的に受け取らないコツ:TEDの説明
Have you ever taken something personally—like a small change at work or a minor inconvenience—and found yourself spiraling into frustration? You’re not alone. In this thought-provoking talk, Heath Butler explores the universal human drive of self-preservation and how it shapes our behavior, decisions, and interactions with others.
和訳:仕事上の小さな変更やちょっとした不便を、自分への個人的な攻撃だと感じて、イライラがつのったことはありませんか?
あなただけではありません。
この考えさせる講演で、ヒース・バトラーは、人間に普遍的に備わる自己防衛本能と、それが私たちの行動、意思決定、そして他者との関わり方にどのような影響を与えるのか説明します。
収録は2024年の10月、動画の長さは10分24秒、動画の後に抄訳を書きます。
☆TEDの記事の説明はこちら⇒TEDの記事のまとめ(1)ミニマリスト的生き方の参考に
ところどころにくすっと笑えるエピソードが盛り込まれたユーモアのあるトークです。
人は物事を個人的に受け取る
実はこの部屋でいちばん大事な人間は私です。
どうしてそんなことがわかるのか?
それは10年ほど前にマクドナルドがコーヒーを変えたとき、私はそれを「個人的に」受け取ったからです。
調べてみると、全国的に供給業者を変更していて、どう見ても質の劣る豆に変わっていました。
「なぜこんな仕打ちを私にする?」と思いました。
なぜグローバルなレストランチェーンがコーヒー豆を変えただけのことを、私はここまで個人的に受け止めたのでしょう?
それは、すべての人間の行動を突き動かしている動機である、自己防衛本能(self-preservation)があるからです。
このことを意識できるようになると、人との関わり方や日々の体験が大きく変わります。
とはいえ、私たちはたいてい、そうした本能が自分や他人にあると気づかず暮らしています。
その結果、フラストレーションや孤立感を覚えたり、「自分のことをわかってもらえていない」と感じたり、ひどいときには「巨大コーヒー企業が私を狙っている」とすら思ったりするんです。
日常生活に現れる自己防衛本能
皆さんも、自覚はなくても、自己防衛の必要性を感じたことがあるはずです。
たとえば、天気予報で雪が降ると聞いて、急いで牛乳やパンを買いに走ったとき。
レジに並ぶとき、カートがいっぱいの人より先に行こうと、少しスピードを上げたとき。
買い物帰りに警察の車を見つけて、急いでブレーキを踏み、「どうか止められませんように」と願ったとき。
私たちの行動は、こうした生存本能に突き動かされています。
マズローの欲求階層説
この生存本能について、マズローは「欲求階層説」で説明しています。
よくピラミッド型の図で表されますが、底辺には「食べ物・水・安全・住居」などの基本的な身体的ニーズがあります。
その上に「所属感・自尊心」などの心理的ニーズがあり、頂点にあるのが「自己実現(self-actualization)」、つまり自分の可能性を最大限に発揮するニーズです。
それぞれの階層のニーズが満たされて初めて、次のレベルへ進むことができます。
そして、自分のニーズが満たされていない限り、本当の意味で自分らしく生きることはできません。
幸いなことに、私たちの多くは食べ物・水・安全といった基礎的なニーズは満たされています。
そのため、今度は「つながりたい」「価値を認められたい」といった心理的なニーズを満たすことが課題になります。
欲求のレベルが上がるにつれて、自己防衛の現れ方も変わっていきます。
もう生き延びるために戦っているのではなく、人間関係や価値観、快適さを守るために私たちは日々戦っているのです。
食べ物を探し回る代わりに、コーヒー豆について大手チェーンにクレームのメールを書く。
それが現代のサバイバルです。
人は自分にどう影響するかを考える
私は過去4年間、「チェンジマネジメント」の分野で働いてきました。
チェンジマネジメントとは、企業が何かを変えるときに、その理由を人々に理解してもらい、その変化を受け入れて成功へ導くためのプロセスです。
私の役目は、人々がその変化に納得し、適応できるようサポートすることです。
変化には、大規模な組織再編のようなものもあれば、小さなソフトウェアのアップデートのようなものもあります。
この仕事で面白いのは、どんな変化が起きても、人々の反応はほぼ同じだということです。
それは、「これって自分にどう影響するの?」という反応です。
この反応自体は悪いことではありません。
なぜなら、私たちは皆、「自分の視点」から世界を見ているからです。
バックパックの実験
この仮説を証明するために、大学時代に実験を行いました。
正確には実験というよりイタズラでした。でも学びがあったので、実験と考えています。
ある学生グループが平日昼に無料ランチイベントを開催していて、多くの学生はランチルームに入る前にラウンジにバックパックを置いていました。
ある日、友人と「全部のバックパックをクローゼットに隠したら面白いんじゃない?」と思いつき、実行に移しました。
隠してから、何が起きるか観察することにしたのです。
ランチが終わると、みんな自分のバックパックを必死に探し始めました。
誰も「全部のバックパックが消えている」ことには気づかず、まずは「自分のカバンがない!」とパニックになっていました。
やがて誰かがクローゼットを見つけ、「ここにみんなのバックパックがある」と気づいたとき、ようやく視点が変わりました。
「どこにあるんだ、私のバックパック?」から、「ここにある、私たちのバックパックへ」と。
この出来事が示しているのは、不確実な状況に直面したとき、人はまず自分のことを考えるということです。
自己防衛と他者への思いやりのバランス
では、自分のニーズを満たしたいという欲求(=自己防衛)と、他人と共に生きていくという現実を、どうやって両立させればよいのでしょうか?
生存競争があると考えると、そこには勝者と敗者がいて、「私かあなたか」のどちらかしかないように思えます。
でも、私たち人間がここまで生き延びてこられたのは、他者が私たちのニーズを満たすのを助けてくれたからです。
そして、その人たちが私たちを助けてくれたのは、彼ら自身のニーズが満たされていたからなのです。
つまり、自分のニーズを満たしたいと思うことは、決して利己的なことではないのです。
人間関係のゴールデンルール
実際、自分のニーズが満たされていなければ、他人を助けることは本当にはできません。
「自分がしてほしいように、他人にも接しなさい」というゴールデンルール(黄金律)は、シンプルな言葉ですが、非常に力強いメッセージを含んでいます。
それは、「自分のニーズを満たすこと」と「他人のニーズを助けること」がつながっているということです。
この両立(duality デュアリティ 二重性)は、とても重要です。
この考え方は昔から存在しており、さまざまな文化、宗教、哲学に見られます。
たとえば中国哲学の「陰と陽(Yin and Yang)」は、すべてのものがつながっていて、相反する力がバランスを取り合いながら存在することを示しています。
それぞれ単独でも価値はありますが、組み合わさることでより大きな力が生まれると考えられています。
ヒンドゥー教の「ナマステ」という言葉も同じです。
「私の中の魂が、あなたの中の魂を認識し、敬意を払います」という意味で、自分と他人、どちらの価値も認め合う姿勢を表しています。
キリスト教では、「自分を愛するように、他人を愛しなさい」という教えがあります。
これらすべてに共通しているのは、自分の価値も他人の価値も、どちらも大切にするべきだということです。
私たちは、自分のニーズにしっかり目を向けると同時に、他人のニーズにも手を差し伸べていく必要があるのです。
コーピングスタンス・モデル
では、どうすれば自分と他人の両方を大切にすることができるのでしょうか?
そのヒントになるのが、家族療法と心理学の先駆者とされるヴァージニア・サティアが提唱したコーピングスタンス・モデル(Coping Stances Model)です。
このモデルでは、バランスが取れた状態を、congruence(コングルエンス 調和、一致)と呼びます。
そしてこのコングルエンスは、次の3つの要素で成り立っています:
・自分(You)
・他人(Others)(個人でも集団でも)
・状況(Context)(いま起きている出来事や環境)
この3つすべてを意識し、考慮できてはじめて、人間関係におけるバランスがとれるのです。
しかし、1つでも欠けてしまうとバランスが崩れ、以下のような「対処行動(コーピング)」が出やすくなるとサティアは述べています:
・相手を責める(blaming)
・相手に合わせすぎる(people pleasing)
・理屈で押し通す(over rationalizing)
・何も考えず流す(irrelevance)
私のコーヒー事件では、何が欠けていたのでしょうか?
「状況」については考えていました。コーヒーが変わったことは事実です。
「自分」の気持ちも把握していました。私はその変化が気に入らなかったんです。
でも私は、「他人」、つまり企業側のことを考えていませんでした。
なぜ変更したのか、その背景や、企業にとってどんな意味があったのかに思いを巡らせることはありませんでした。
あなたにも、「つい個人的に受け取ってしまった出来事」があったかもしれません。
そんなとき、「自分」「他人」「状況」の3つの視点をすべて意識すれば、反応の仕方が変わり、日常がもっとラクになるかもしれません。
ある人事担当者のとまどいと気づき
私が職場で実際に体験したエピソードをご紹介します。
あるとき、人事担当者が、フルタイムの仕事を強く希望していたパートタイム職員に対して、正式にフルタイムのオファーを出しました。
誰が見ても「これはすぐに受けるはず」と思えるようなオファーでした。
ところが、締切が近づいても返事が来ず、人事担当者はイライラし始めました。
そこで私は、もしその職員がオファーを受けた場合、どんな影響があるのかを一緒に考えてみることにしました。
勤務時間が増えれば、当然家庭で過ごせる時間は減ります。
彼女には小さな子どもが2人おり、生活リズムも変えなければなりません。朝は早くなり、帰宅は遅くなり、これまで不要だった新たなデイケアの手配も必要になります。
また、彼女は現在の職場の同僚たちが大好きでした。 新しい勤務地に移れば、人間関係をゼロから築き直すことになります。
私たちが状況をひとつひとつ確認していくうちに、人事担当者の視点に変化が現れました。
それまでは、このオファーは、自分にとっては、たくさんするべきタスクの1つでした。
でも、人に与える影響や相手の生活全体に与えるインパクトに目を向けたら、ただの業務が人の人生に関わる大きな転機だということに気づいたのです。
人事担当者が最初に考えていたのは「自分の立場」(=期限までに返事が欲しい)だけでした。
この状態はバランスが崩れており、結果としてフラストレーションが生じていたのです。
しかし、「自分」「相手」「状況」という3つの視点をしっかりと考慮できたとき、担当者の中にあったいらだちが消え、代わりに共感と理解が生まれました。
「人間の行動は自己防衛本能によって動かされている」――この事実に気づくだけで、私たちの反応は変わり、日々の暮らしがもっとラクになります。
・誰かが作業を遅らせたとき
・荷物が見当たらないとき
・コーヒー豆が変わったとき
以前のようにイライラしたり、落ち込んだりすることが少なくなるでしょう。
この気づきは、私たちに自分自身のニーズに目を向けると同時に、他人のニーズにも配慮できる力を与えてくれます。
もし、こんなふうに考え方を変えられたらどうでしょう?
「私はこの部屋にいる一番大事な人」から、「私はこの部屋にいる、大切な人たちの中の1人」へ。
人間である限り、自己防衛本能は持ち続けます。
でもそのことを知っていれば、人にも、自分にも、もっと優しくなれます。
私は、あなたが今日のトークを「個人的に」受け取ってくれることを願っています。
人間関係改善に役立つほかのプレゼン
なぜ人は憎むのか? 思いやりのスイッチが切れる理由(TED)
5つの椅子と5つの選択、もっと上手にコミュニケーションをとる方法(TED)
豪華なプレゼントはいらない~人を特別な気分にさせる秘訣(TED)
自分・相手・状況
バトラーさんのトークは、日常よく聞かれる「相手の立場に立って物事を見よう」という人間関係のアドバイスと基本的には同じです。
ただ、相手の気持ちを想像する以上の視点、つまり状況(コンテクスト)という第三の要素が入っているところが目新しいと思いました。
多くの人は、「自分」と「相手」という2つの視点で物事を捉えがちです。
「私はこう思う」「あの人はこう考えているかも」というように。
でも、このトークでは、「今それがどんな状況で起きているか」という「背景や環境(=コンテクスト)」も含めて捉えると、バランスが取れると伝えています。
バランスが取れるとは、より具体的かつ実用的な共感を持てるということです。
「店のコーヒーが変わった」という出来事に対しても、
・自分:好きじゃない
・相手:企業としての判断
・状況:経費削減や流通の変化などの事情
この3つの観点で見ると、ただ単に「嫌だ、ムカつく」という反応から抜け出せるのです。
日常生活で、何か、頭に来ることやいらっと来ることがあったら、あまり個人的に受け止めず、3つの観点から考えてみてください。
多くの場合、相手にはあなたを傷つける意図はないし、周囲の状況も自分がコントロールできないところで動いています。