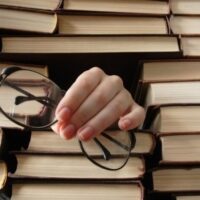ページに広告が含まれることがあります。
健康のために1日1万歩、歩こうとよく言われますが、この1万歩という数字に根拠があるのでしょうか?
今回紹介するTEDトークは、1万歩という数字は、マーケティングの産物だったと伝えます。
タイトルは、10,000 steps: Fact, fiction, or fad? (1万歩:事実か、フィクションか、それとも一過性の流行か?)
ハーバード大学の公衆衛生学の教授で、身体活動を専門とする研究者、アイミン・リー博士(Dr. I-Min Lee)の講演です。
何歩歩けば、健康にいいのか? そんな疑問に答えてくれます。
1万歩、歩いたほうがいいのか?
収録は2024年、動画の長さは7分27秒。英語字幕あり。動画のあとに抄訳を書きます。
☆TEDトークの説明はこちら⇒TEDの記事のまとめ(1)ミニマリスト的生き方の参考に
短いし、シンプルなコンセプトなのでわかりやすいトークです。
歩数を競う健康プログラム
1日1万歩という規準は、万歩計を販売する会社が作ったって知っていましたか?
本当に健康のためには毎日1万歩、歩く必要があるのでしょうか?
今日は、このテーマに関する最新の研究結果を紹介します。
数年前のこと。当時、私の勤務先が従業員の運動量を増やすための健康促進プログラムを始めました。
私は運動に関する研究をしていたため、そのチームのリーダーを任されました。
参加者全員にフィットネストラッカーが配られ、毎日の歩数を記録して、データベースにアップロードすることになりました。
そして、毎週、各チームの累積歩数が集計され、最も多く歩いたチームがその週の勝利者となります。
残念ながら、私たちのチームは一度も勝てませんでした。
チームのメンバーは私のような人たち、つまり多くが女性で、全員が中高年でした。
そのフィットネストラッカーには、初期設定の目標歩数がありました。
そうです、お察しのとおり、1万歩です。
あるチームメイトがこう言いました。
「この歩数目標って無茶よ。私の年齢じゃ、絶対に無理だわ。」
この一言でこんな疑問を持ちました。
「この1万歩という数字、そもそも何が根拠なんだろう? 誰が決めて、どんなデータがあるんだろう?」
1万歩はメーカーのキャッチフレーズ
調べてみると、この1万歩という数は、1960年代半ばの日本で生まれたものでした。
当時、山佐時計計器株式会社という会社が、世界で初めて市販用歩数計を販売し始めたのです。
商品の名前として選ばれたのが、「万歩計(Manpo-kei)」という名前です。
万歩(Manpo)とは日本語で1万歩の意味。
つまり、「1万歩を測る計器=万歩計」という、非常にわかりやすく魅力的なネーミングだったのです。
当時の広告を見ると、白、黒、ベージュ、赤の4色から選べたようです。
1964年に東京オリンピックが開催された直後だったこともあり、世の中は運動への関心がとても高まっていました。
日本の研究者たちは、「1日1万歩のウォーキングが心臓病のリスクを下げる可能性がある」と信じていました。
しかし当時は、実際に1万歩以上歩く人と、そうでない人を比較した研究は、まだ存在していませんでした。
1日、1万歩に効果があるか?
そこで私は、1日に歩く歩数と健康の関係について実際のデータを調べてみたいと思いました。
特に知りたかったのは、1万歩が、健康と不健康を分ける境界線かどうかという点です。
私は、全米規模の女性を対象とした大きな研究「ウィメンズ・ヘルス・スタディ(Women’s Health Study)」の共同ディレクターを務めています。
この研究に参加した約1万7千人の女性に、2011年から2015年にかけて、研究用の精度の高いフィットネストラッカーを1週間装着してもらいました。
1日の歩数と、その後の死亡率を関連づけて分析できるのではないかと思いました。
2019年、私たちはこのデータをもとに、画期的な研究結果を発表しました。
歩数と健康の関係
次の問いの答えを検証したもの。
「健康のために、1日に本当に1万歩も歩く必要があるのか?」
リサーチに参加した女性たちは、比較的高齢で、当時の平均年齢は72歳です。
結果は、1日1万歩に達していなくても、それよりずっと少ない歩数であっても、健康に有益な効果があることがわかりました。
たとえば、この研究で最も運動量が少なかった5%の女性は、1日あたり約2,000歩しか歩いていませんでした。
それに対して、3,000歩歩いていた女性は、2,000歩の人たちよりも死亡率が低かったのです。
さらに4,000歩歩いていた人は、3,000歩の人よりもさらに良い結果が出ていました。
つまり、簡単に言うと:
少しでも歩けばいい。もっと歩けばもっといい。
ということです。
興味深いのは、7,500歩に達したあたりで、効果が頭打ちになるという点です。
つまり、1万歩歩いた女性と、7,500歩歩いた女性の間では、死亡率のさらなる低下は見られませんでした。
ですから、こう言い換えるべきかもしれません:
「少しでも歩けばいい。もっと歩けばもっといい。でも、限度はある。」
効果が頭打ちになる歩数
私たちの研究結果が発表されてから、他の研究者たちも同様の研究を行い、知見が増えていきました。
それらの研究では、男性も対象に含まれており、年齢別の違いも検証されていますが、どの研究も同じ結論が出ています:
「少しでも歩けばいい。もっと歩けばもっといい。でも、限度はある」
これは男女ともに当てはまる結果です。
ただし、年齢によって限度の歩数に違いが見られました。
高齢者(60歳以上):効果が頭打ちになるのは 6,000~8,000歩
若年~中年層(60歳未満):効果が頭打ちになるのは 8,000~10,000歩
つまり、健康効果を得るために1日1万歩も歩く必要はないのです。
歩くスピードで差があるか?
次に気になるのは、速く歩くのとゆっくり歩くのでは違いがあるのか、ということです。
私たちの「女性の健康に関する研究」では、高齢の女性たちを対象にした結果ですが、歩く速さは関係なく、重要なのは歩数そのものであることがわかりました。
同じ歩数を歩いた2つのグループを比べたとき、速く歩いたグループの死亡率が、ゆっくり歩いたグループより低いということはなかったのです。
その後、別の研究もいくつか行われましたが、結果は必ずしも一致していません。
私たちと同じ結論に至った研究もあれば、「速く歩いたほうが、やや追加の健康効果がある」と示した研究もあります。
ですから、この点についての明確な答えはまだ出ていません。
現在も研究が進められており、近い将来には、合意が得られるでしょう。
さて、健康とは、生きる・死ぬという話だけではありませんよね。
心疾患やがんのリスクはどうか?
身体機能や認知機能、認知症、生活の質(QOL)など、他の健康指標との関係は?
比較的新しい分野のため、現在わかっているのは、主に死亡率や心疾患のリスクについてです。
ただ、心臓病や死亡率以外のこと、たとえばがんや認知症、生活の質などについては、まだはっきりしたことはわかっていません。
でも今、世界中の研究者たちがそうしたテーマに取り組んでいて、これから数年のうちに、歩くことがどんな健康効果をもたらすのか、もっと詳しくわかってくるでしょう。
少しでいいから体を動かそう
もちろん、1日1万歩を目指せる人は、それを目標にしてかまいません。
その意欲は素晴らしいですし、決して1万歩という数値を否定しているわけではありません。
ただ、世界にはたくさんの人がいます。高齢の方、持病を抱える方にとっては、1万歩が「難しい」どころか「不可能」なのです。
そういう方にとって、たとえ1万歩に届かなくても、2000歩でも多く歩けば、しっかり健康効果があるとわかるのは、大きな励ましになります。
歩くことができない人たちがいるということも、私たちは忘れてはいけません。
そうした方に対しては、他の種類の身体活動を使って同じことが言えます。
少しでも体を動かすこと。そうすれば確実により健康になります。
とにかく歩きましょう。動き続けましょう。
そうすれば、人生が長くなるだけでなく、1日1日をもっと元気に、楽しく過ごせるようになります。
///// 抄訳ここまで ////
運動に関するほかのプレゼン
ウォーキング・ミーティングのススメ。健康にいいし仕事もはかどる(TED)
なぜ運動するのを面倒に感じるのか?あるいは断捨離を始められないのか?(TED)
数字より日々の実感が大事
新しい習慣は21日で作られる、1日1万歩歩くと健康になるといった数字による指標は広く知れ渡りますが、それが必ずしも事実、もしくは、科学的な裏付けがあるものとは言えません。
ただ単に、数字だとわかりやすいから、「そうなんだ」と皆が思ってしまうだけ。
今回のトークでも、「1日1万歩」という目標は、実はマーケティングから生まれたものであり、それより少ない歩数でも十分に健康効果があると示しています。
いろいろな研究がありますが、適度に歩くことが体に悪いという結果が出ているものはありません。
歩くことは、確実に健康にいいので、もし、「1万歩も歩けない」と思って、ほとんど歩いていないのならば、少し歩くことから(室内でもOK)体を動かすことを始めることをおすすめします。
私は、50歳のときにスロージョギングをはじめて、今も、毎朝、走ったり歩いたりしていますが、運動を始めてからほとんど風邪をひかなくなりました。
50歳の私がスロージョギングを始めたらみるみる健康に~そのメリットとは?
少しでも歩けば健康効果があるし、メンタルにもいいです。自分のライフスタイルや体調に合わせて、ぜひ、ウォーキングを生活に取り入れてください。