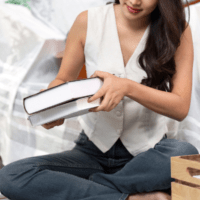ページに広告が含まれることがあります。
今回は、学び方に関するTEDトークを紹介します。
タイトルは、The Learning Blind Spot: Why We Miss What Matters(学習の盲点:なぜ大切なことを見落とすのか)。
プレゼンターは、教育工学を専門とするサーシャ・ヴァッサー(Sasha Vassar)さんです。
なぜ、たくさんノートを取ったのに、講義の内容が思い出せないのか?
なぜ、がんばって勉強しているのに、理解が深まらないのか?
彼女は、学びの過程で私たちが無意識に見落としてしまう盲点について、具体的な事例を交えて説明しています。
何かを学んでいる方はもちろん、お子さんの勉強をサポートしている親御さんにも役立つ内容です。
収録は2025年の4月、動画の長さは15分30秒。動画のあとに抄訳を書きます。
☆TEDの説明はこちら⇒TEDの記事のまとめ(1)ミニマリスト的生き方の参考に
英語はとてもわかりやすいですし、ユーモアもあるので、英語の勉強素材としておすすめのトークです。勉強の仕方も学べますので一石二鳥ですね。
学べないのは盲点があるから
もし、学びにおける最大の課題のひとつが、知性の欠如や努力不足ではなく、盲点だとしたらどうでしょう?
学生たちは毎日、講義に出席し、蛍光ペンで線を引いたり、びっしりとノートを取ったりして、「内容をマスターしている」と信じ込んでいます。
私もかつては、まさにそういう学生のひとりでした。詳細なノートを取るのが好きで、それによって「学んでいる」「何かを成し遂げている」と感じていました。
でも、ここに問題があります。
実は、こうした学習法の多くは、効果がありません。
しかも、今ではChatGPTのようなツールで、学生たちは驚くほどすばやく答えを手に入れることができます。
けれどそれでは、本来、深い学びに必要な苦闘するプロセスがありません。
研究によれば、学生たちがこうした非効率な学習法に頼るのは、けっして怠けているからではありません。ただ、それしか知らないのです。
私が子どもの頃、母は試験の前夜になると、教科書を枕の下に入れて寝るようにと言いました。
もちろん、これは学習に最適な方法ではありません。寝心地は最悪でしたし、試験の成績にもまったく効果はなかったと思います。今にして思えば、効果がないとわかっている学習法の典型でした。
どうしても見つからないバグ
私は学者になる前、テストエンジニアとして働いていました。私の仕事は、コードのバグを見つけて、それを再現し、こわすこと。
でも、どんなに注意深く見ても、どうしても見つからないバグが、いつも何個かありました。まるで「見えないバグ」のように。
今でもよく覚えていることがあります。
何時間もデバッグして、ありとあらゆる方法を試しました。頭が変になりそうなくらい、全部、ダブルチェックして、コードの一部を書き直してみても、まったく解決しませんでした。
プログラミング経験のある方なら「セミコロン(;)の付け忘れじゃないの?」と思うかもしれませんが、もっと複雑なバグでした。
目の前にあるはずのバグが見えなかったように、学生たちもまた、自分の学習法の欠陥に気づかないことがあります。
彼らはちゃんとやっていると信じています。でも実は、その学び方では、深く理解することができません。
ちなみに、あのときは、同僚が私の画面をちらっと見ただけで、ほんの数秒でバグを発見しました。
こうした経験は、学生にもまったく同じように起きます。私がバグに気づけなかったように、彼らも学びの中の大事なポイントを見逃しています。
なぜ私はバグを見逃したのか? そして学生たちは、なぜ重要な学びの瞬間を見逃してしまうのか?
選択的注意の欠如
実際に皆さんにも試していただきます。ちょっとしたテストをやってみましょう。
[The Monkey Business Illusion という有名な実験の動画が映し出されます。これは複数の人がパスをしている映像を見ながら、「白いシャツを着た人が何回パスをしたか」を数える課題が出されるもの]
何人かの方が笑っていたのが聞こえました。ということは、私が「見逃すだろう」と思っていたものに、ちゃんと気づいたんですね。
さて、ここで質問です。パスの回数を数えた方はいますか? 正解は16回です。
それから、画面中央に現れたゴリラを見た人は? 何人かは気づきましたね、すばらしい。
ただし、ゴリラが出ると知っていた人はどうでしょう? 途中でカーテンの色が変わったのに気づきましたか? 黒いTシャツを着たプレイヤーの1人が、途中で画面から出て行ったことに気づきましたか?
ああ、皆さんは「選択的注意の欠如(inattentional blindness)」なんて無縁みたいですね。
今皆さんが見たのは、選択的注意の欠如と呼ばれる現象です。
この分野の多くの研究は、Simons(サイモンズ)と Chabris(シャブリス)による1999年の研究に基づいています。
もしかしたら皆さんの中にはゴリラを見逃さなかった方もいるかもしれませんが、学生たちは、勉強中に、目の前にある「ゴリラ=重要なこと」に気づかないことがよくあります。
授業に出て、素晴らしいノートをたくさん取ったのに、教室を出たあとで「結局、何の話だったんだっけ?」となったこと、ありませんか?
よくある話です。そして私は、ノートを丁寧に取りすぎると、実際に話されている内容を聞き逃してしまうと考えています。
認知がオーバーロードする
学生が私の講義でコードを書きながらついてくるときも、私がコードや構文、構造について説明していても、その内容を聞き逃してしまうことがよくあります。
これらすべての話は、認知負荷理論(Cognitive Load Theory)と呼ばれるある学習理論に基づいています。
私たちの作業記憶(ワーキングメモリ)は非常に限られていて、一度に保持できる情報は5~7個程度だという理論。つまり、一度に5~7個以上の要素を扱うのは難しいのです。
学生の作業記憶がいっぱいになると、入ってくる情報をすべて処理することができなくなります。
その課題に多くの認知的エネルギー(集中力や思考力)を必要とするほど、何か重要なことを見落とす可能性があがります。
つまり、内容が難しければ難しいほど、学ぶ人の負荷が増して、オーバーロードを起こしやすくなるのです。
たとえば、買い物袋をいくつか持っているところを想像してみてください。
1個、2個、3個、5個ぐらいまでは、両手を使えば何とか運べますよね。
でも、6,7、8、……13個と増えていったら、どれかを落としてしまいます。これが認知のオーバーロード(過負荷)です。
プログラミングの経験がある方なら、コードがずらっと並んだ画面を見て「うわっ」と思ったことがあるでしょう。
画面に表示されている情報が、自分の作業記憶の処理能力を超えているからです。
コードをデバッグするときに最も大変なのは、この情報量の多さです。
膨大な数の論理が書かれた行が一斉に「私を見て!」と主張しているようなもの。
でも、これはプログラミングに限った話ではありません。エッセイや研究論文、情報が詰まったあらゆる文章を見るときに同じことが起こります。
チャンクで考える
では、認知の過負荷にどう対処すればよいのでしょうか?
まず、コードを見て、その後視線を外してください。脳に処理する時間を与えます。
そして、再び見直すときに、一度にすべてを理解しようとしてはいけません。
チャンク(小さなかたまり)に分けましょう。扱いやすいサイズに分割して、少しずつ読み解いていきます。
コードでは、インデント(字下げ)や空白、括弧などのスタイルを使って、論理的なかたまりを作ります。これにより、コード全体に圧倒されず、読みやすくなります。
エッセイも同じです。段落を分けたり、コンマや句読点で文を整理したりして、情報を区切って処理しやすくしています。
チャンクに分けると、巨大で威圧的な、混沌とした情報の塊に見えていたものが、小さくて処理可能なものに変わります。
チャンクごとに、パターンを見つけたり、見慣れた構造に気づいたり、まだ理解できていない部分をはっきりさせることができます。
コードの「壁」をチャンク化できれば、小さなかたまりごとに集中できます。それぞれを調べて、理解していく。そうやって、少しずつコード全体がつながって、意味を成すようになります。
これはつまり、脳が処理をし、振り返り、理解を深める「余白」を与えることです。ステップバイステップで、チャンクごとに進んでいきます。
作業記憶がいっぱいだと起きること
ある研究者たちは、「見落とすのが難しいゴリラ(Invisible Gorilla)」のような明らかなものを見逃すのは、見ていなかったからではなく、ワーキングメモリ(作業記憶)がいっぱいで、記憶を保持できなかったからだと考えています。
脳が一度はそれに気づいたけれど、重要じゃないと判断して消してしまったのです。
私は『ゲーム・オブ・スローンズ』を夢中になって見ていましたが、あの有名な*スターバックスのカップの事件には、まったく気づきませんでした。
せりふに集中していたため、脳がそれ以外の情報を処理しなかったのです。
これは授業中のメモ取りにもあてはまります。私たちは、メモを取ることに集中しすぎて、講師が実際に話していることや提示されている情報を見落としてしまうことがあります。
この「圧倒された状態」と「見落とし(盲点)」を避けるには、自分でコントロールできる雑音を減らすことも有効です。
今の学生は常に情報の洪水の中にいます。通知、SNS、複数の画面、マルチタスク、すべてが同時に注意を引こうとします。
教える側が複雑なスライドや同時進行の課題、わかりにくい説明などで、無意識に認知の負荷を増やしてしまうこともあります。
こんな状況では、何が重要なのかを考えることがとても難しくなります。
研究では、認知の負荷が高すぎると、記憶の定着が悪くなり、問題解決能力が落ち、パターンの発見や理解が進まなくなることがわかっています。
たとえば、講義中にスマホでかわいい動画を見て、講義も聞いて、スライドも確認して、ついでに近くの人をチェックして……そんなことをしていれば、大事なポイントをたくさん見逃してしまうのは当然です。
では、どうしたらいいでしょうか?
気を散らすものを排除する
そうした気を散らすものを取り除くことです。
スマホはフォーカスモードにして、しまっておきましょう。パソコンも通知を止めましょう。
授業中に長々としたメモを取るのはやめて、キーワードだけ書いておき、あとからその意味を掘り下げるようにしましょう。
一度にいろんなことをしようとせず、ひとつのチャンクを、ひとつずつ処理していきます。
学習中の見落としや盲点は、一見たいしたことがないように思えるかもしれません。でも、それらもしっかりと、特定の結果(consequences)を引き起こします。
たとえば、プログラミングの理解不足は、深刻なセキュリティの欠陥や、予期しないバグを生むかもしれません。
その瞬間に学びそこなったせいで、単位を落としてしまう可能性もあります。
失敗はやり方を変えるサイン
失敗した瞬間はつらいけど、いいこともあります。
ときには、コースを再履修し、盲点を乗り越え、より深く理解できます。
私たちは、間違えるから、自分が知らないことについて多くを学べます。
プログラミングでも、最初からうまく動くコードより、失敗するコードのほうが学べることが多いです。
私が博士課程にいたとき、3回連続で実験に失敗したことがありました。
その時点で「1年分の人生を無駄にした」と感じ、ものすごく落ち込みました。
落ち込みから抜け出すのはとても難しく、その「盲点」にとらわれてしまいました。
でも、今でも覚えているのは、そのときに指導教官が言ってくれた言葉です。
その一言で、私は失敗のとらえ方が変わりました。
彼女はこう言いました:
「いつもうまくいく完璧な実験などあり得ません。そうでなければ、私たちがやっていることは、すでに知っていることの証明に過ぎません。もしそうなら、私たちは何の変化も起こさず、進歩もなく、何も新しいことを学ぶこともできないでしょう。」
失敗とは、やり方を変えるチャンスです。
足りない部分を補い、盲点に気づき、もう一度やり直して、より良くするための機会です。
これはプログラミングだけでなく、学び全般に対する姿勢にも通じます。
何度も練習する
最も大切なことの一つは、練習を何度もすること。
問題の種類や解決方法のボキャブラリーを増やすことです。
練習を重ねれば重ねるほど、不注意による見落とし(inattentional blindness)に対処できる力がつきます。
私はいろいろなタイプのバグを見てきたおかげで、次に同じようなバグに出会ったとき、より早く見つけられるようになりました。
でも、どんなにがんばってもバグが見つからず、「目の前のゴリラ」を完全に見落としてしまうこともあります。
そんなときに最も効果的なのは、いったん問題から離れてみることです。
それが、脳の負荷をリセットし、再び処理できる状態に整えてくれます。
少し時間をおいて問題に戻ると、最初よりもずっといいパフォーマンスができることが多いです。
しばらく時間を置くと、記憶がリセットされ、最初にとったやり方にしばられなくなるからです。
その結果、脳が新しいつながりを作り始め、まったく違う視点から問題を見られるようになります。
認知負荷をうまく管理できたとき、私たちは初めて「ずっと目の前にあったもの」が見えるようになります。
そう、「ゴリラ」は最初からずっとそこに立っていて、私たちが気づいてくれるのを待っていたのです。
まとめ:うまく学ぶコツ
冒頭で、私は見つけられなかったバグの話をしました。
それと同じように、私たちは学んでいるとき、「盲点」に直面しています。
私たちは効果的な学習法をしていると思っていますが、実はそれが負荷をかけすぎて、深い理解に至らないのかもしれません。
大事なのは、
・同じことを繰り返して、違う結果を期待しないこと
・視点を変えること
・気を散らすものを取り除くこと
・アプローチを変えること
こうすれば、あなたが探していた答えは、実は最初からずっと、目の前にあったと気づけるかもしれません。
///// 抄訳ここまで ////
*ゲーム・オブ・スローンズのスターバックス事件:現代のスターバックスの紙カップが画面に映り込んでしまった制作側のミス、見落とし。
学習や認知に関するほかのプレゼン
ワーキングメモリ(作業記憶)をうまく使って目の前のゴールを達成する(TED)
自分の能力を自分で見限ることの恐ろしさ、できると信じることの素晴らしさ(TED)
上手になりたいと思っていることをきっちり上達させる方法(TED)
シンプルライフで大事なものが手に入る
情報や気を散らすものが多すぎると、脳に負荷がかかりすぎて、肝心のことを学び損なうと伝えるトークを紹介しました。
これは、学びの場面だけでなく、日常生活でも言えることです。
余計なものや情報が多すぎて、それらの管理に時間や意識を奪われ、不用品の視覚的ノイズにさらされる暮らしでは、大事なことに集中できません。
しかし、現代はこういうことが起こりやすい状況です。
トークで言っていたように、私たちは情報の洪水の中にいますし、買い物がとても簡単なので、そこまで必要でないものをたくさん買ってしまいます。
しかも、一度買ってしまったものは、使っていなくても、「捨てるのはもったいない」となかなか捨てませんよね?
これら、すべてのことが、私たちの脳に大きな負荷をかけています。
その結果、本当に大事なものを見落とすと思います。
ヴァッサーさんがすすめていた「気を散らすものを取り除くこと」は、シンプルライフで叶えられます。
何かを学びたい人、大事にしたいことがある人。そんな方には、ぜひシンプルライフを試してください。