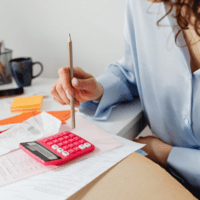ページに広告が含まれることがあります。
捨てるのが怖くて片付けが進まない人のために、不安をやわらげてうまく捨てる方法を7つ紹介します。
人はもともと現状維持を好み、失う痛みを強く感じます。
そのため「後で必要になるかもしれない」「人にもらったから申し訳ない」「お金をかけたから無駄にしたくない」などなど、考えてしまいます。そして、頭では「もういらない」とわかっていても手放せません。
私も「片付けたいのに不安で捨てられない」というメールをいただくことがあります。
そんな恐怖を小さくする実践的な工夫を解説しますね。
1.怖さの正体に気づく
何が怖いのか、その正体をはっきりさせると、不安が小さくなります。
なぜ、あなたは捨てることをためらうのでしょう?
怖さの背景には「失敗したくない」「判断を間違えたくない」という心理があります。「大切な思い出を失うのが怖い」という不安もあるかもしれません。
自分が感じている恐怖を具体的に言葉にしてみると、そこまで恐れることはないと気づくものです。
本当に怖かったとしても、解決策を考えることができます。
たとえば、あとで必要なときにそれがないのが怖いなら、代用品があるかどうか、また手に入れられるか調べればいいでしょう。
罪悪感を恐怖と感じているなら、罪悪感が少ない手放し方を検討すれば捨てやすくなります(6番を参照してください)
ただ「怖い」と感じているだけだと何も行動できません。
恐怖を具体的な言葉にすると、漠然と怖がっていた状態から、恐怖との向き合い方を考えられるようになります。そうすれば、捨てることに一歩近づけますよ。
2.すぐに決めずに寝かせる
迷ったものはいったん保留にして、様子をみましょう。
いきなり「捨てるか残すか」を迫られると、恐怖が強い人は手元に置いてしまいます。
迷ったものは、即決しようとせず、考える時間を取りましょう。箱や袋に入れて日付を書き、押し入れなどにしまってください。
数か月後にその存在すら忘れていたら、もう必要ないとはっきりわかります。使わずにすんだのですから、「なくても大丈夫」と納得できるでしょう。
この方法は、「捨てたら後悔するかも」という怖さをやわらげてくれます。それがなくても暮らしに支障がないと、確認できるからです。
「もういらないかも」と思うものを棚や引き出しから取り出して別の場所に置くと、収納が使いやすくなります。
ものが少ない生活のよさを味わうことができるので、これも捨て活を後押ししてくれるでしょう。
3.捨てやすいものから始める
捨てるたびに、すごく考えてしまうなら、負担が少ない捨てやすいものから捨てましょう。
いきなり思い出の品や高価なものに取り組むと、「大事な思い出がなくなる!」「もったいなさすぎる」と捨てない言い訳が次から次へと出てきます。
最初は、冷蔵庫の棚で眠っている期限切れ食品や、穴のあいた靴下、古い雑誌など、誰が見ても処分に迷わないものから片付けましょう。
捨てやすいものでも、ものはもの。ガラクタが減るとスッキリします。
「捨てることができた」という成功体験も得られるので、自信もつきますよ。
捨て活はトレーニングのようなもの。経験を重ねれば重ねるほど素早く判断して、さっと捨てられます。
最初は1日1個で十分です。練習のつもりで捨てましょう。そのうち、恐怖に負けないようになります。
4.迷ったときの質問を用意する
あらかじめ捨てる基準を決めておくと判断が楽になります。
「これは今の生活に役立っているか?」「同じものを今もう一度買うだろうか?」「自分の生活にプラスになっているか?」など、3つほど、イエス・ノーで答えられる質問を用意しましょう。
質問に対して「はい」と答えられないなら、今の自分には必要がないと考えてください。
人は感情に流されやすいので、明らかなルールを作ったほうが、捨てる決断がしやすくなります。
自分だけの質問リストをつくり、迷ったら、それに照らして判断してください。ここは、事務的にやることをおすすめします。
捨てるものがわからない時に使ってほしい、物の価値を見極める10の質問リスト。
5.思い出は写真や記録に残す
思い出の品は、かさばらない形で残しましょう。
思い出が詰まったものを捨てるのがすごく怖いと感じる人はたくさんいます。大切な記憶がなくなってしまうと恐れるのです。
重要なのは、記憶であって、必ずしもものそのものではありません。写真に撮ったり、エピソードを日記に残したりすれば、実物を捨てても、思い出は消えません。
私は娘が小学校で使っていたアジェンダ(連絡帳みたいなもの)から、娘が書いた文字を少しだけ撮って残しました。
あとで見返すと、懐かしく感じると思ったからです。実際は全然見ませんが、あとで思い出したいと思うなら、このように重要な部分をコンパクトにして残すだけで充分です。
思い出のアイテムを全部持つ必要はありません。重要な記憶はいつまでも自分の中に残ります。
6.罪悪感が少ない手放し方をする
罪悪感が強い人は、罪悪感を感じにくい手放し方をしましょう。
寄付やリサイクルに回せば、誰かに活かしてもらうことにつながるので捨てやすいでしょう。売れるものならフリマアプリやオークションなどで売ってもいいです。
罪悪感がやわらぐと、不用品を手放すのがずっと簡単になります。
また、罪悪感そのものの見直しも役立ちます。罪悪感の元になっている考え方を変えましょう。たとえば、
・高かったから捨てられない⇒今使っているかどうかのほうが大事
・もらったから申し訳ない⇒ものを残すより、気持ちを受け取ったことが重要
・思い出があるから手放せない⇒思い出はものではなく心の中にある
・たくさんあるほうが安心⇒必要な分だけあればそれでいい
「不用品を捨てるのは悪いことだ」という思い込みから自由になれば、強い抵抗を感じずに手放せます。
7.自分で自分を励ます
怖いと思ったら、自分で自分を励ましましょう。
「これは未来の私を楽にする一歩だ」「私は自分の生活を大事にしている」。こんなふうに声に出すだけで、不安がやわらぎます。
私たちは言葉で思考します。自分が口にする言葉が感情を生み、行動につながります。つまり、使う言葉が気分や行動の質を左右するわけです。
ポジティブな言葉(大丈夫、少しずつできる)を使うと、脳は安心し、創造性や回復力が高まります。
迷ったら、「これは私を助ける選択だ」と言うのはどうでしょう?
恐怖はゼロにはできませんが、言葉の力で軽くすることはできます。 自分を励ますフレーズを用意し、実際に口にして、捨て活を後押ししましょう。
******
捨てるときの怖さを軽減するコツを紹介しました。
ものを捨てようとするとき、不安になったり、ためらったりするのはごく自然なことです。
不用品はわりとさっさと捨てる私ですが、捨てる前は、「これ、あとでいるかも?」と少し考えます。
実際は、「あとでいる」と思って残しても結局何年も使わない体験を何度もしました。
今捨てなくても、どうせあとで捨てるんです。
だから、その恐怖や不安に行動を決めさせる必要はありません。
不用品を捨てても生活の安全はおびやかされません。むしろ暮らしやすくなります。
こう言われても、まだ恐怖がある人は、この記事に書いた方法をぜひ試してください。
自分なりに折り合いをつけられるようになり、捨て活が進みます。