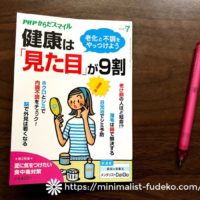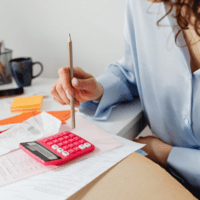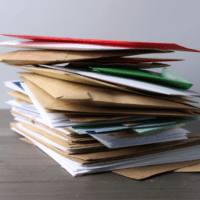ページに広告が含まれることがあります。
ものを手にいれるときに自分が感じていた未来への期待。これを考えると、そこまでがんばらなくても、不用品を捨てられます。
そもそも、なぜこれを買ってしまったのか?
こんなふうに、そのアイテムを手に入れた理由を思い出してみましょう。
不用品を捨てられない時、「もったいない」という感情だけでなく、手に入れた当時の自分の気持ちや、何かを期待していた記憶に執着していることがあります。
自分が何を期待していたのか? これに気づくと、「前はそう思っていたけど、現実はそうはならなかった」「これはもう、十分役目を終えた」と納得できて、処分しやすいのではないでしょうか?
この記事では、未来への期待がものを増やすこと、そしてその期待について考えればものを減らせることを説明します。
あなたがしがみついていたのは、ものではなく、期待だったのかもしれません。
なぜ増えてしまったのか考える
片付けというと、多くの人がいらないものを捨てることだと考えます。私も長年そうしてきました。もちろん、それで部屋はきれいになります。
ただ、ものを捨てるのがすごく苦手な人もいますよね。
そんな人は、どうしてそのアイテムが家に入ってきたのか、考えてみてください。
なぜあなたは、こんなにものを増やしてしまったのでしょうか?
これは、自分を責めるための問いではありません。ものが増えた背景にある、自分の思いや行動を見つけるための質問です。
この点を無視していると、いくら減らしてもまた同じことを繰り返すかもしれません。
たとえば、使っていないまま取ってある布や糸。「あのときは本気でまたソーイングを始めたかったから買ったんだ」と気づけば、それを手に入れた理由や、今も持っている理由が見えてきます。
そして、今はあまりソーイングをする状況でないことや、その気持ちがなくなったことと照らし合わせれば、「もうこれはいらないな」と納得できるでしょう。
ものを招いたのは未来の自分への期待
ものを買う時、私たちは無意識に「これがあれば、未来の自分のためになる」と思っています。
たとえば、
ダイエット器具:今度こそ使ってやせる
手芸の材料:時間ができたら始めて楽しむ
本や教材:あとで読んで学ぶ
ストック食品や紙製品:いざというとき、これがあるとあわてなくてすむ
どれも悪いことではありません。私たちは未来をよくしたいと思って買っているのですから。けれども、その未来が来なければ、ものだけが残ります。
問題は、自分の期待がこもったものをなかなか手放せないことです。それは、単なるものではなく、理想の自分や夢の象徴だからです。
「いつか使うかもしれない」と思うものを前にして手が止まるとき、私たちは、「今の自分」と「期待していた自分」とのあいだで揺れているのかもしれません。
たとえば、私は、「この本を読めば自分がいいほうに変わるだろう」と思って、何冊も買っていた時期があります。でも実際は、読む時間が取れず、積読のままでした。
今思えば、本に期待していたのは、読んで楽しむことではなく、「読めばきっと何かが変わるはず」という実態のない魔法のような効果でした。
ものに過剰な期待を寄せると、持っているだけで「やったつもり」「ほしい状態を手に入れたつもり」になります。しかし、実際はそれを使わない限り、求めていた未来を得ることはできません。
なかなか捨てられない「なりたい自分になるために買った物」を断捨離する方法
期待で増えた出番のないものたち
未来への期待が作った出番のないものたちにはこんなものがあります。
「そのうちやるつもり」のグッズ
私は以前、家の中に語学の教材が山ほどありました。本棚の隅に並べて、いつか全部読むつもりでした。でも、結局どれ1つページを開きませんでした。
買ったときは、教材をちゃんと読んで実力がついた私になりたかったのです。しかし、実力は道具を持っただけでは身につきません。
使わなかったのは、それが当時の私の生活スタイルや優先順位に合っていなかったからです。
中国語の教材と本を断捨離するのに12年かかった私がとうとうたどりついた真実とは?~ミニマリストへの道(18)
備えのつもりが、ただの不安の表れ
「災害が心配だから」と、水や缶詰、乾電池をかなりため込んでいた読者がいました。あまりにためこみすぎて、居住スペースを圧迫するほど。
いくら災害の多い日本でも、毎月特定の地域にコンスタントに地震や台風が起こることはありません。
非常用の品々は、どれも使われないまま、賞味期限切れになったものもあったといいます。
ストックを持つことが安心につながるのは事実ですが、備えのためではなく、不安をなくすために買っていると過剰になりがちです。
未来はどうなるかわからないので、不安になろうと思えばいくらでもそうなれるからです。
人のために取っておいたもの
自分だけでなく、人が使うことを期待して持つものもあります。誰かの役に立つかもしれないという期待のせいで、ものが増えていくケースです。
「娘が使うかもしれない」「お客様が来たときに必要かも」こう思って取っておいたものが山ほどある人もいるかもしれません。
でも、親と子どもは別の生活をする別の人間。子どもにはそれぞれの人生と生活があるので、あなたの不用品を使ってくれるとは限りません。来客についても、実際に人が来る予定があれば、必要なときに必要な分を用意すればいいのです。
期待が終わったことに気づけば、手放せる
ものを手放すとき、「まだ使えるのに」「高かったのに」と迷いが出るのは、そのものに託した期待がくすぶっているからかもしれません。
でもよく考えてみると、こうした期待の多くは、すでに終わっています。
たとえば、「ダイエット器具を使うつもりだった」と思っていても、現実にはここ数年まったく使っていないのなら、もう使うつもりはないんです。
今は運動をする時間や気力がないから、その器具に込めた「頑張る自分」への期待は、すでになくなったと見ることはできないでしょうか?
もう何も期待していないのに、それに気づかずものを残していると、ものだけが生活の中で取り残されていきます。
その結果、見るたびに罪悪感や焦りが生まれ、気持ちの負担になるでしょう。
捨てにくいものを見つけたら、こう自問してください。
「私は、これに何を期待していたのか?」「その期待は、今も生きているのか?」「もはや何も期待していないなら、もう持っていなくてもいいのでは?」
こう考えれば、「もうこの商品の役目は終わった」と自然に手放せるでしょう。
それは、ひとつの節目を認めることです。
「やっぱり無理だった」とがっかりしたり、あきらめたりすることではなく、「これはもう、今の私には関係がない」と冷静に現実を受け入れること。
手放すことは、過去を否定することでも、夢を捨てることでもありません。それは、今の自分に合った選択をし直すことです。
*****
ものを手放しにくいとき、手に入れたとき何を期待していたのか、考えてみることをおすすめしました。
最初は、「これを使って何かしたい」「こんな人になりたい」という思いがあったはずです。
ただ、それが実現しなかったのなら、現状に合わせて、所持品をアップデートするべきです。そうしないと、死蔵品はどんどんたまるでしょう。
人の生活も気持ちも変わります。その変化に合わせて、身の回りを整えていくと、暮らしの質はあがります。