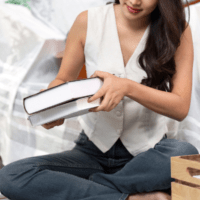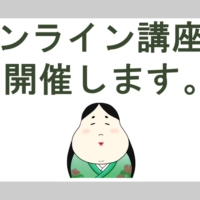ページに広告が含まれることがあります。
私たちは「ものをきちんと収納したから片付いた」と勘違いしますが、それはなぜでしょうか?
収納してもガラクタは減らないのに。
こんな勘違いをしてしまう理由と、本当はどうしたらいいのかこの記事で紹介しますね。
収納すれば片付くのか?
部屋が散らかってきたとき、収納ボックスや引き出しにものをしまい、見た目をスッキリさせることが多いと思います。
床や机の上が片付き、部屋が広くなったように感じると、「ああ、片付けられた」とホッとしますよね? でも、これで満足していると、暮らしはなかなかシンプルになりません。
収納はものを減らす行為ではないからです。ものの総量は変わらず、ただ場所を移動させただけです。
けれども私たちは、収納を終えた瞬間に片付けが完了したと思います。次にものが散らかってきたとき、同じことをするので、押し入れや棚の中にどんどんものが押し込まれ、そのうち収集がつかなくなります。
散らかった部屋で、「おかしいな? ちゃんと片付けているのに」。こんなふうに思うなら、ぜひ、続きを読み、収納すると片付いたと思う幻想の正体を知りましょう。
視覚的にスッキリする
ものを収納すると、見た目がきれいになるので、「ちゃんと片付いた」と思います。
脳は、五感の中でも視覚情報に最も強く影響されます。視覚は情報量が多いので感情や行動に大きな影響を与えます。
床や机の上にものが積み重なっている雑然とした光景は「ごちゃごちゃしている」「片付いていない」という気持ちにさせます。逆に、散らかっていたものを収納ボックスや引き出しに移して視界から消すと、たとえものの量が全く減っていなくても、脳は「片付いた」と判断します。
しかし、見た目がきれいになったからといって、ガラクタが多いという現実は変わりません。
収納スペースの中に詰め込まれたものは、依然としてそこに存在し続けます。
むしろ、奥に押し込まれたせいで、使いにくくなるし、存在自体を忘れてしまうこともあります。押し入れが一杯になると、さらに収納グッズを買い足し、ものを詰め込む結果になるでしょう。
実際、すきまというすきまを収納に使っている家もめずらしくありません。
視覚的なスッキリ感は、その瞬間だけです。時間が経てばまたものがあふれ、再び片付けが必要になります。
収納すると達成感がある
収納すると、「たくさん働いた」という達成感や充実感を得られます。
ものを分類し、箱や引き出しに入れ、棚や押し入れに収める。こうした作業をせっせとすると、体を動かすことになり、短時間で成果が見えるため、自分がいかにもがんばったように思えます。
机の上に積まれた書類を全部ファイルに入れて棚にしまえば、机がスッキリし、「すごく片付けた」とうれしくなります。ビフォー・アフターの光景が大きく変わるので、「今日は頑張った」と自分をほめたくなるでしょう。
こんなふうに、実際はガラクタをそのまま持っていても、作業の充実感が満足感を高めます。
「がんばった」と思うこと自体は悪いことではありません。実際、机の上はきれいになって使いやすくなっているでしょう。
問題は、ガラクタは何一つ減っていないことです。
収納の問題は、時間が経てばまた散らかることにあります。
特に、複雑でめんどくさい収納をすると、取り出すのも戻すのも手間がかかるため、しまうより床や机の上に置いてしまうことが増えます。
がんばって収納してスッキリさせても、そのうちまた散らかります。その結果、「片付けても片付けても終わらない」状態になります。
片付けのゴールは達成感を得ることではありません。ものを減らして暮らしやすくすることです。
収納すれば捨てなくてもいい
収納してしまえば、とりあえずその日は、捨てなくてすみます。
現状を維持できるので、収納してしまったほうが簡単です。
ものを減らすことは、心理的にも体力的にも大変です。人は現状維持が好きなので、できればものを捨てたくありません。
とりあえずしまっておくという選択肢は、何も捨てなくていいし、片付けた気分も得られる、きわめて都合のいい方法です。
「まだ使うかもしれない」と思っている服や雑貨を収納ケースに入れると、「これを持っていてもいいんだ」という気になりませんか?
ふだん見えない場所に置けば、邪魔にも感じません。収納してしまえば「手放さなくても大丈夫」という口実ができるのです。
しかし、いったん、「これ、捨てたほうがいいかも?」と思ったものを、箱の中にきれいに並べたからといって、「絶対捨ててはいけないもの」になることはまずありません。
捨てる判断を先延ばしにしたものは、その後も使わないことが圧倒的に多いもの。
押し入れやクローゼットの奥で眠っていた箱の中身を、数年後に開けてみたら「こんなもの持っていたっけ?」と思うことはよくあるはずです。
収納という名の断捨離の先延ばしは、収納スペースを圧迫し、新しい収納グッズを買う原因にもなります。
どんなにきれいに収納しても、自分が何をどれだけ持っているかわからなくなります。図書館や博物館のように一つひとつ分類して、体系的に管理すれば別ですが、記憶だけに頼っていると、全体量も内容も把握できません。
文化とメディアが作った「収納=正解」イメージ
収納すれば片付いたと思い込む背景には、長年、メディアや文化が作り上げてきた価値観があります。
雑誌やテレビ、近年ではSNSが、美しい収納の写真や収納術の特集を繰り返し発信してきました。その結果、「収納が上手=片付けができる」というイメージが広く定着したと思います。
テレビや雑誌のビフォー・アフター企画では、散らかった部屋が収納グッズや家具で整然と変わる様子が映し出されます。
劇的な見た目の変化は視聴者の印象に残りやすく、多くの人が、片付けとは収納を工夫することだと考えてしまいます。実際には、撮影のために一時的に整えただけかもしれないのに。
SNSでは、ラベルや色でそろえた収納棚、パズルのようにぴったり収まった引き出しの中身などがたくさんシェアされます。
こうした写真は見ていて気持ちがよく、「私もこうしたい」と思わせます。
この美しさは演出だと思います。少なくとも、一瞬を切り取った写真であり、忙しい生活の中で、ずっと維持できるとは思えません。
見せるための収納であり、使うための収納ではないのです。
あまり現実的でない収納法であっても、脳は、秩序、対称、整列に安心感を覚えるので、私たちは、整然と並んだスパイスボトルや、色別に並んだクローゼットの写真を見るのが好きです。
また、日本の国土は狭いので、限られた空間で多くのものを持つために、収納を工夫することが生活術として重視されてきました。
その結果、ものを減らすという選択肢より、収納方法が先に浮かぶ人が多いと思います。
◆関連記事もどうぞ◆
私は収納が得意、狭いところにびっしりしまい込み、無駄なものなんて持っていないと思っていた。
片付かない理由は、収納という名の「決断の先延ばし」をするから
おわりに:本当の解決法はものを捨てること
収納は片付けの最終段階です。一番最初にやってしまうと、ものだらけの状況を改善できません。
本当に暮らしをスッキリさせるには、収納する前に「要・不要」の判断を行い、いらないものは収納しないことが重要です。
不用なものの管理に、意識や時間を使うのはもうやめましょう。迷ったまましまい込むと、再び取り出すこともなく、スペースが埋まっていくだけです。
本当に使うものや、生活に必要なものだけを残し、使う頻度や目的に応じて、収納してください。
片付けのゴールは、しまうことではなく、減らすことです。
ものが少なければ、収納グッズにお金を、収納テクニックに時間をかける必要もなくなります。
ものの管理がしやすい心地いい暮らしは、不要品を捨てることから始まります。