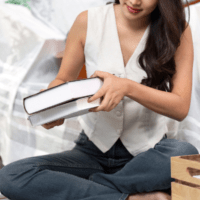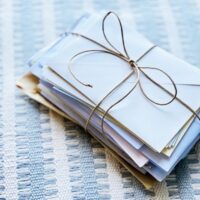ページに広告が含まれることがあります。
もったいない気持ちが引き起こす不自由と、この気持ちにしばられないコツを紹介します。
「もったいない」と思ってものを捨てないでいると、かえって生活しづらくなります。
ものを大事にするのは大切な価値観です。食べ物を粗末にしない、ものを最後までちゃんと使う。どれも望ましい行動です。
でも、ものがあふれている現代は、もったいない気持ちが裏目に出ることもあります。
高かったから捨てられない、まだ使えるから置いておく。そんなふうにして使わないものをいつまでも家に残すと、さまざまな不便が生じます。
どんな困ったことが起こるか、以下で具体的に見ていきましょう。
「もったいない」が積み重なるとどうなる?
「もったいないから捨てない」という判断は、一度きりなら生活に大きな影響はありません。
でも、毎回、そう思って捨てないでいると、じわじわと暮らしにくくなります。
もったいない気持ちが強いと、処分を先送りします。
本当は必要ないとわかっていても、「もったいないから」というもっともらしい理由があるので、その場で捨てる決断ができないのです。
小さな先送りを何度もして、とりあえず残したものがどんどん増えます。
そうして残したものは、使わないまま収納の奥に押し込まれ、やがて、その存在を忘れてしまいます。こうして、押入れや棚の中に死蔵品がたまっていきます。
また、暮らしをアップデートすることもできません。
ライフスタイルや生活環境が変わると、必要なものは変わります。
適度にものを新陳代謝すべきですが、「まだ使えるからもったいない」「高かったからもったいない」こんなふうに考えて、持ち物を見直そうとしません。
結局、もったいないと思うせいで増えてしまった死蔵品は、以下のように暮らしを不自由にします。
使えない収納、動けない部屋
死蔵品がたまると、まず収納を思うように使えなくなります。
クローゼットや押入れの中が、いらないものでいっぱいになり、大事なものもそうでないものもごちゃごちゃになります。
収納が機能していないと、ものの出し入れをするたびに余計な手間が増えます。
どこに何があるのかわからなくなり、探し回ったり、奥に押し込んだものを取り出すのに、すべてを引っ張り出さなければならなかったりします。
出すのが面倒なので、収納の奥にあるものは、ますます使わなくなります。
収納しきれないものは、そのうち、床や家具の上に置かれるようになります。すると動きにくくなります。
歩くときに体を横にしてすり抜けたり、窓やドアの開閉がスムーズにできなかったり。家具や荷物が通り道を邪魔し、家の中を自由に行き来することすら難しくなるかもしれません。
自由に使えない収納と、ものでふさがれた生活空間。これが、もったいない気持ちが奪う最初の自由です。
探し物と片付けに奪われる時間
もったいながる気持ちは、時間の使い方にも影響があります。
収納スペースにはものがいっぱいあるので、必要なものをすぐに取り出せず、日常的に探すことになるでしょう。
たとえば重要な書類や保証書を探すとき、関係のない古いレシートや不要な資料が混ざっていれば、見つけるまでに余計な時間がかかります。
風邪薬を飲もうとしたとき、古い薬の箱が残っていれば、使える薬を探すのに手間取ります。
このように、探す・整理する時間は、短時間ですが、毎日のようにやっていると、思いのほか時間を取られます。これは、不用品がなければ費やさなくていい時間です。
ものが多いと掃除や片付けにかかる時間も長くなります。
床のあちこちにものが置いてあれば、掃除機をかける前にどかさなければなりません。棚に細々としたものが乗っていると、ほこりを取るの一苦労です。
つまり、ものを動かしたり端に寄せたりすることに時間を取られるわけです。
いつか何かに役立つとものを取っておくせいで、私たちは貴重な時間を失っていると考えることができます。
本来なら休息や趣味に使える時間を、不用品の管理や探し物に使います。せっかくの時間を有意義なことに使えないので、人生の質が下がります。
不用品が生む心の重荷
捨てなかったものは、場所や時間だけでなく、心の自由も奪います。
タンスや押入れを開けたとき、着ない洋服や使わない道具がぎっしり詰まっていると、「ちゃんと使わなきゃ」「お金を無駄にした」と罪悪感や自己嫌悪を抱きます。持ち物があるせいで、セルフイメージが悪くなります。
「いつか使えるかも」「そのうち何かに使おう」という気持ちがあるせいで、過去に引っ張られ、新しいことを始めるハードルがあがります。
ふと興味を持ったことを始めようと思っても「前に買った道具を使っていないのに」とブレーキがかかり、結局チャレンジできなことはないでしょうか?
服や日用品も「まだあるから」と自分の好みや生活に合わないものを我慢して使い続けることもありますよね。
さらに、不用品が目に入るたびに小さなストレスになります。
「片付けなきゃ」と思いつつ、手をつけられないまま時間だけが過ぎる。やらなければならないことのリストが増えていき、気持ちの余裕がなくなっていきます。
つまり、もったいない気持ちを優先すると、必要ないものを守ることにエネルギーを使って、本当に大事にしたいことや、やりたいことに意識を向けることができません。
もったいない感情と上手につき合うコツ
ここまで見てきたように、もったいない気持ちは自分を不自由にします。
この感情を完全になくすことはできませんが、気持ちに振り回されない工夫はできます。
捨てようとしたその瞬間、「もったいない」と思っても、次の瞬間に考え方を変えればいいのです。
何がもったいないのか、冷静に考えてみましょう。
お金がもったいないと思うなら、すでに使ってしまったお金は戻ってこないことを思い出しましょう。
捨てずに持ち続けても、支払った代金が返ってくるわけではありません。もう手元にないものを取り戻そうと躍起になるより、今の自分がラクになる選択をしたほうが建設的です。
さらに、ものは、皆で共有する資源だと考えてみてください。
使わないまま眠らせるより、寄付やリサイクルに回せば、誰かの役に立ち、資源を循環させることができます。
捨てるのはものを無駄にするもったいない行動だとは思わず、手放すのは次の人につなぐことだと考えましょう。
「もったいない」と思ったとしても、そのアイテムが、実際に必要であるとは限りません。
感情を優先して残す前に、「いまの生活で本当に使っているか」「これからも出番があるか」という視点で判断してください。
客観的な事実をもとにして、捨てるか残すか決めれば、シンプルに暮らせます。
ものを残せば、すべて未来の自分に負担がかかることを忘れないようにしましょう。
今日「もったいない」と残したものは、明日以降もずっと自分が管理し続けることになります。
収納スペースがなくなり、掃除や整理の手間が増え、さまざまな不自由を被ります。不用品をいま手放すことは、未来の自分を楽にすることだと考えてください。
◆関連記事もどうぞ
⇒捨てられないモヤモヤを解消~ “もったいない”を手放す7つの心理と解決策
⇒捨てるのはなんだかもったいない、そう言って捨てない人におすすめの3つの考え方。
⇒もったいないから捨てない。この決断のせいであなたが失っているたくさんのもの。
******
「もったいない」と感じて、使わないものを残してしまうせいで、暮らしが不便になることを説明しました。
「もったいない」と感じるのは、人間の本能的な反応です。
ものが貴重だった時代には、この感覚が生活を守ってくれました。けれども、ものがあふれる現代に、そのまま従うと逆に不自由を招いてしまいます。
もったいないという感情が、常に最適な判断につながると考えるのをやめましょう。
本能に流されるのではなく、いまの暮らしに合った選択をしてください。
「もったいない」と思った瞬間は、自分の価値観を見直すチャンスだと思います。
もったいない⇒残す、ではなく、もったいない⇒本当にそうなの? 残すと私のためになるの? と考えてください。
自分に役立つものだけを残すことを繰り返すと、次第に余計なものにしばられない生活になります。