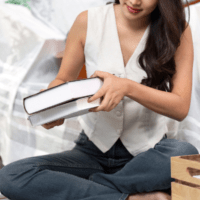ページに広告が含まれることがあります。
もしかしたらあとで使うかも?
この気持のせいで、不用品をいつまでもキープしてしまうことがあります。
今回は、そういうものを手放すコツを紹介します。(最後にエッセオンラインの記事の告知あり。)
もしかしたら? が汚部屋を生む
人は何かを失うのが嫌いなので、厳然たる不用品でも、まだきれいな製品や新品同様の品物は、「もしかしたら~」と考えて手放しがたく感じます。
あなたの家にこんなものはありませんか?
・何十年も前から箱に入れっぱなしの書類
・故障したまま放置してある家電
・かつて趣味に使っていたグッズ、スポーツ用品
・主婦になってから全然使っていないOL時代の衣類やバッグ
・いつか時間ができたら読みたい未読本
・いつからあるのかわからない思い出の品の入った箱
これらの品物を、今日捨てて、完全に縁を切る気になる人はそう多くないでしょう。
今日までずっと使っていなかったけど、もしかしたら、明日/3か月後/半年後/3年後/5年後/10年後に、状況や自分の気持ちが変わって使うんじゃないか、そのときにこれがないと困るじゃないの、と思うのです。
しかし、家の中が倉庫のようになってしまうのは、こういう「もしかしたら~」と思うものが多すぎるからです。
「もしかしたら使う」と思ったら、それを元の場所に戻す前に、以下のことをしてみてください。
1.とりあえず置き場所を変える
捨てなくてもいいので置き場所を変えてください。
といっても、倉庫の奥深くにしまいこむわけではありません。
「もしかしたら使うかも箱」みたいな入れ物や袋を用意して、捨てたいけど捨てられないものをしまいましょう。
箱には中身と日付を書いて、わりとアクセスしやすい場所に置きます。
日常使っているクローゼットやタンスは、あくまで現役の品物を入れるべきであり、リタイア寸前や、事実上リタイアしてしまっている品物には専用の置き場所を与えて様子をみましょう。
半年~1年出番がなかったら、もう不用と判断して捨ててください。
箱の中に入れて、移動させたら、高い確率でその箱の中身は忘れてしまいます。
捨てようとするとき、「もしかしたらいる」と思ったとしても、それらの品物は、本当はずっと前に自分の生活や心から離れていたのです。
私自身、この方法で、食器、レシピ、キッチンツールなどを断捨離しました。
料理本を断捨離(全捨て)した。いくらレシピがあっても料理上手にはなれない
押入れも棚も、「もしかしたら」と思う製品が場所をとっているので、移動させれば、いきなり使いやすくなります。
2.リストを作ってみる
全然使っておらず、「もしかしたらいるかも」という理由だけで残しているものをリストにしましょう。
15年前福袋に入っていた帽子、去年友達からもらったスカーフ、5年前に買った本、ずっと動きのないストックのボールペンなどなど。
手書きでも、スプレッドシートに入力してもいいので、1つひとつざーっとリストアップしてください。
リストを作っているときに、かなりのものは、「もう捨てよう」という気になります。
というのも、「もしかしたらいるかも」と思っているとき、意外とその対象をしっかり見ていないからです。
なんとなく大事な気がしているだけです。
リストを書くために、その品物をちゃんと見て、具体的な言葉にすると、ぼんやり「大事なもの」の仲間に入れていたものをもっと現実的に捉え直すことができます。
リストを書いても、やはり1つも捨てられないですか?
そんな人は続きを読んでください。
3.地に足をつける
もしかしたら必要になる、と思うとき、今の現実はたいして問題にしていません。
頭の中で、勝手にタイムトラベルして、来るかどうかわからないときについてだけ考えています。
現実にも目を向けてください。
もしかしたら、あとでいるかもしれないけれど、そういうものがいっぱいあるせいで、今、自分がすごく苦労していることにも。
先日断捨離のメリットを紹介しましたが⇒気持ちが穏やかになる~不用品を捨てる意外なメリット(その2)
「もしかしたらグッズ」がたくさんあると、この記事に書いた逆のことが起きます。
・物が多すぎて、見るからにストレス
・毎朝、着るものにさんざん迷う
・手持ちの収納スペースだけでは間に合わず、外部に倉庫を借りて、お金を払って収納する
・休日は整理整頓と掃除でつぶれる(若い頃の私はそうでした)
・なんとかきれいにするために、また収納グッズを買う
・探しものばかりする
・必要なときに出てこないので、同じものを二重に買ってしまう
これらは、今本当に起こっていることであり、来るかどうかわからない未来の話ではありません。
スペース、時間、意識、お金には限りがあるので、今現実に起こっている問題から対処すべきではないでしょうか?
4.良いシナリオも考える
もしかしたら後でいるかもしれない、必要になるかもしれない、使うかもしれない。
そう思っているとき、悪いことしか考えていません。
あとで必要になるときに、これがなかったら、とてもとても困る。新たに買うのに、ものすごくお金がかかる、いや、もう2度と手にはいらないかもしれない。
こんな感じです。
これは、最悪のシナリオです。
しかし、現実には、そういう事態になることは非常にまれです。
なぜなら、本当に大事なものは、そもそも捨てたりしないから、捨てるかどうか迷うものは、そこまで大事ではなく、捨ててもたいして困らないものだから。
つまり、
A.あとで必要になる可能性は思ったより少ない
B.仮に必要になっても、そのピンチを切り抜ける方法はいくらでもある
これが現実です。
捨ててしまっても、世界が崩壊するわけではないです。
それなのに、人は、捨てたあとに、最低最悪のことが起きるかのように心配し、そちらしか見ません。
でも、そうならない可能性もありますよね?
何かを捨てたあとに起こることを、「最低最悪のことが起きて、私は生きる気力を失い、毎日がまっくらで、ざんげの値打ちもない」という筋書きばかりにせず、そうならないシナリオも考えてください。
もしかしたら
・捨てたあとすぐに忘れて、何も起きない
・スペースがあいて開放感を感じる
・4年後ぐらいに必要になったけど、100均ですぐに調達し、事なきを得た
・捨てたあと、はずみがついて、結果的にミニマリストになってしまった
こんなことも起きるかもしれないのです。
最悪のシナリオを考えたら、必ず最高のシナリオ(それが無理ならニュートラルな現実に即したシナリオ)も考えるくせをつけましょう。
5.捨てる恐怖を手放す
誰でも、ものを捨てるときに、不安や恐怖を感じるものです。
それはこのシリーズで書いているとおり⇒物を手放すことに対する不安や恐怖に向き合う(その1)~どこから始めたらいいの? という不安。
不安になるのは普通のことですが、何を捨てるときにも、いちいち恐怖を感じていたり、ものすごく怖れていたりするなら、その恐怖を手放しましょう。
ものを捨てることをそんなに恐れる必要はありません。何年も家の中で放置されていたものを捨てたところで、そこまで恐ろしいことは起きませんので。
今は、2023年で、日本でふつうに暮らしていれば、生存を脅かされることはそうそうありませんよね。
昔は、物を捨ててしまうと、もう2度と手にはいらなくて、死に直面したり、村八分になる可能性があったかもしれません。
具体的にそれがどんなシチュエーションなのか、私には想像できませんが。
でも、今はそういうことは起きない。
ですから、捨てる恐怖を拡大させるのはやめましょう。
何かを行うとき、恐怖に突き動かされていると、心は平穏ではいられません。
恐怖ではなく、それ以外の欲望、たとえば、自己実現の欲求、探究心や好奇心などをベースに断捨離したほうが、同じ捨てる行動をしていても、ずっと楽しいはずです。
心配性は自分で克服できる。恐怖と向き合うことを学ぶ(TED)
番外:捨てて経験値を得る
もしかしたら、あとで使うかも、と思ったとしても、ちょっと勇気を出して捨ててみてください。
最初は、そこまでハードルの高くないものを捨てるといいでしょう。
実際に捨ててみると、「あとでいると心配していたけど、捨てたら思ったより快適だ。もっと早く捨てればよかった」と思うでしょう。
そう思えなかったとしても、いきなり恐ろしいことが起きないことはわかるはずです。
こうやって、「捨てても大丈夫だった体験」を積み重ねると、捨てることを恐れる気持ちは薄れていきます。
捨てようとする瞬間、本能的に「もったいない」と思うでしょうが、そのあと、直近の体験から集めたデータを検証すればいいのです。
もしかしたら、
・すぐに後悔した
というデータが残っているかもしれません。でも、
・今でも、捨てたもののことを時々思い出すけれど、そこまでつらくはない
・捨てたその日から暮らしやすくなった
・もっとたくさん捨てたくなった
こんなデータも取得できると思います。
結局、実際に捨ててみないと、そのあとどうなるか、自分がどういう心境になるかはわかりません。
害の少なそうなものからせっせと捨てて、データを集めてください。
■関連記事もどうぞ⇒将来、必要になるかもしれない:物を手放すことに対する不安と恐怖(その8)
旅の荷物を減らす
エッセオンラインに新しい記事がアップされました。今回は、旅行に行く時の荷物を少なくするコツです。
⇒60代ミニマリストの「旅の荷物を少なくするコツ」7つ。どんな旅行にも使える基本とは | ESSEonline(エッセ オンライン)
旅行に行く予定のある人もない人も、ぜひ、お読みください。
人生も旅ですから。
*****
私の場合、何かを捨てたら、すぐ忘れました。
忘れたので、捨てて後悔したものもありません。
雑誌の編集者たちに、捨てて後悔したものはないのかと何度も聞かれましたが、本当にないんです。
むしろ、もっと早く捨てておけばよかったと思っています。