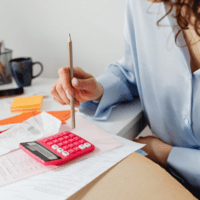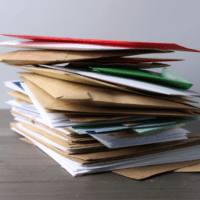ページに広告が含まれることがあります。
直感を鵜呑みにしないほうがいいと教えてくれるTEDトークを紹介します。
タイトルは、Should you trust your gut?(直感を信じるべきか?)精神科医のAlex Curmi (アレックス・クルミ)さんのトークです。
直感を信じる?
収録は2025年4月。動画の長さは15分。英語字幕あり。動画のあとに抄訳を書きます。
「私は直感で決める人だから」と思い込んでいる人にぜひ見ていただきたいトークです。
決断の質が人生を決める
今日は、本能、直感、私たちがどうやって決断を下しているかといったことについてお話しします。
これはとても重要なテーマです。
私たちが下す決断は人生に大きな影響を与えますし、「決められないこと」が多くの人にとって大きな苦しみの元になっているからです。
数年前、私の心理療法のクライアントのひとりが、新しい恋愛について話してくれました。この話の中では彼を「スティーブ」と呼びましょう。
彼は恋をしており、新しい交際相手のことをとても楽しそうに話していました。
何度も「彼女は素晴らしいパートナーになると思う」と言い、ふたりで将来の人生を築く姿が想像できるとも話していました。
ですから、交際を始めて数か月しか経っていないにもかかわらず、一緒に暮らすチャンスが訪れたとき、彼がためらわなかったのも不思議ではありませんでした。
迷うことすらありませんでした。彼には直感があったのです。すべての直感が、「これでいい」と示していました。
しかし、8か月後、スティーブはその関係が壊れてしまったと言いました。
彼のパートナーは、次第に感情的に攻撃的になっていったのです。突然、怒りを爆発させ、夜通し彼を怒鳴りつけ、彼が家族や友人と過ごすことを責めるようになりました。
スティーブは関係を修復しようと努力しましたが、うまくいきませんでした。
「どうして、こんなふうに間違ってしまったのだろう?」と、彼はこのできごとを信じられないと語りました。
このように、時には、私たちの直感が完全に間違っていることもあるのです。
日々、意思決定に追われる私たち
精神科医の私のもとには、直感を信じた結果、うまくいかなかったと相談に来る人がたくさんいます。
今、私たちは日々、無数の決断を迫られています。
仕事、お金、恋愛、子どもを何人持つか、どこに住むか、ワインをもう1杯飲むかどうか、ケーキをもう1切れ食べるかどうか。
あまりにも多くの選択肢があり、圧倒されてしまいますよね。
人生が複雑になるにつれて、決断の数も増えていきます。
しかも、「すべての選択には正解がある」というプレッシャーまであります。
もちろん、すばやくて、強烈で、モチベーションをかき立てるような無意識の本能が役に立つ決断もあります。
たとえば、暗い路地を歩いていて、怖くなり「ここから離れたい」と思ったとしたら、その直感を疑うべきではありません。
私が問題にしたいのは、何週間、何か月、あるいは何年もかけてゆっくり進んでいくような、つまり、私たちの人生に大きな影響を与えるような複雑で長期的な決断です。
直感を信じる文化
このような問題に直面したとき、社会や文化はしばしば、私たちの存在に関わる不安を和らげようと介入してきます。
私たちの文化には、偽りの二項対立を持ち出して、人生をわかりやすく単純化しようとする傾向があります。
たとえば、
右派か左派か?
経済優先か環境重視か?
個人の責任を信じるか、それとも社会制度の変革を信じるか?
このトークのテーマに関しても、同様の偽の二択が用意されています。
直感・衝動・感情を信じるべきか? それとも、冷静で硬直した論理や理性を信じるべきか? という問いです。
私たちは、直感にとても興味を持っています。
過去10年間で、直感(gut feeling)、直感を信じる(trust your gut)、自分を信じる(trust yourself)といったキーワードの検索数は85%も増加しています。
世界中の名だたる会議でもこのテーマで議論されています。
私が思うに、現代の西洋社会は明らかに直感を信じる文化(trust-your-gut culture)へと傾きつつあります。
それはさまざまな形で現れています。
・資格のない恋愛コーチたちが、人生の大きな決断をするときには「衝動に従え」と言う
・暗号通貨の成功者たちが、「リスクを恐れるな。少しの決断力があれば1%の勝者になれる」と説く
・ネット上の陰謀論者たちが、マイクロチップからワクチン、地球が平らかどうかまで何でも議論する
これらの現象に共通しているのは、時間をかけること、専門性を磨くこと、熟考や内省、反省といった行為は、もはや不要だという考えです。
むしろ、本能に従えばいい。その本能を支えるために、自分の直感に合う事実を探すべきだと言うのです。
もし今、ある事実が自分の直感と合わなければ、「新しい事実を手に入れればいい」と言います。
個人の興味に最適化された情報プラットフォームがあふれた世界では、かつてないほど簡単にこれを実現できてしまいます。
直感はとても危ういもの
直感を信じる文化にはいくつか問題があります。
第一に、そもそも「直感」とは、私たちの経験のどの部分を指しているのでしょうか?
それは思考なのでしょうか?
それとも、感情? 記憶? 「お腹の奥で感じるような感覚」なのか、もしくは「頭の片隅でささやくような声」つまり、良心と呼ばれるようなものでしょうか?
それとも野心や不安でしょうか?
第二の問題は、今挙げた私たちの経験を構成するあらゆる要素が、実はとても誤解を招きやすく、偏りやすいという点です。
直感を信じるべきではない理由
これから、直感を信じるべきではない理由を4つお伝えします。
1:進化論的な観点から
私たちの心理は、現代とはまったく異なる環境の中で進化してきました。
たとえば「人前で話す」という状況を考えてみましょう。
もし何千年も前に、私が皆さんの前で話していたとしたら、今とはまったく違う状況だったでしょう。
もっと命に関わるような大きなリスクがあったはずです。このトークの結果によって、得るものも失うものも非常に大きかったでしょう。
もし間違ったことを言えば、部族から追い出されるかもしれません。そうなると、それは死を意味することすらあったのです。
現代人が人前で話すことに強い恐怖を感じるのは、ある意味、当然なのです。
一方で、行動遺伝学の研究から、ある人たちが、神経症傾向(neuroticism)と呼ばれる特性を持ちやすいことが分かっています。
この特性を持つと、人はより悲観的になりやすく、不安を感じやすくなります。
こうした特性は、たとえば敵対する部族や野生動物、天候の変化などに常に注意を払う必要があった昔なら、とても理にかなっていました。
でも、今のように比較的安全で、むしろ人前で堂々と話せる人が有利になる世界において、この特性は果たして役に立っているでしょうか?
2:精神分析的な観点から
ジークムント・フロイトの娘であるアンナ・フロイトは、かつては過激とされていたものの、現在では広く受け入れられている、防衛機制(defense mechanism)という概念を提唱しました。
これは、私たちがある出来事に対して最初に抱く心理的反応は、子ども時代の経験、とくにトラウマ的な体験の影響を強く受けているという考えです。
たとえば、虐待される家庭環境で育った人がいたとします。
その人は、身を守るために、怒りで反応する癖を身につけたかもしれません。
当時、そう反応するのは、正しかったのかもしれません。それがその人を守り、命を救った可能性もあります。
ですが、その反応が今、恋人との関係などで本当に役立つでしょうか?
今その人に必要なのは、おそらく、愛情やつながり、親密さですが、直感を信じると、怒りで反応するクセが抜けないままになります。
3:知覚(Perceptual)の観点から
今、脳の構造、特に、網様体賦活系(もうようたいふかつけい reticular activating system 脳幹にある神経細胞のネットワーク)の働きについて、多くのことが解明されつつあります。
網様体賦活系は、外界から受け取る膨大な情報の大部分を無意識にフィルターにかけて、自分にとって重要だと感じるごくわずかな情報だけに焦点を当てます。
重要と判断されるものは、たいていの場合、自分の目標・期待・可能性に対する信念によって決まります。
こうした「選択的注意」の考え方は、今では有名になったゴリラの動画*によって広まりました。
(*バスケットボールとゴリラの被験者実験動画。人は明らかに動画にあるものでも見落とすことを示すもの)
これはYouTubeだけの話ではありません。日常生活のあらゆる場面で起きています。
たとえば、新しく車を買おうとしているとします。
トヨタ車が気になっていたら、街を歩くたびに目に入るのはトヨタ車ばかり。他の車種は自然と視界から外れます。
場合によっては、私たちの知覚そのものが歪んでいることもあります。
たとえば、社交に不安のある人がパーティーに行ったとしましょう。
笑っている人たちがいると、「自分のことを笑っているに違いない」と思ってしまうことがあります。
本当はただ楽しそうに笑っているだけなのに。
それは、「人に笑われているかもしれない」という本人の期待(思い込み)に合致した知覚なのです。
4:哲学的な観点から
仏教のような、伝統的な叡智(wisdom traditions)では、訓練されていない心について、重要なことを教えてくれます。
それは、私たちの心は本能に導かれると、しばしば機能不全に陥るということです。
本能とはたとえば、
・欲望(cravings)
・嫌悪(aversions)
・妄想(delusions)
仏教では、こうした状態に振り回されないように、マインドフルネスなどの実践を通じて、徐々に自分の心を知っていくべきだと説いています。
そうすれば、心に自然と浮かんでくるあらゆる思考や衝動の奴隷にならずにすみます。
スティーブの本能的な反応
直感に裏切られた私のクライアント、スティーブに話を戻します。
彼の人間関係における最初の本能的な反応は、相手に気に入られようとする(ピープル・プリーザーになる)ことでした。
彼の直感が、「相手にとって最高のパートナーになれるよう、自分を合わせよう」と彼に促していたのです。
つまり、彼は自分の価値観で相手を見るのではなく、相手の期待に自分を合わせようとしていました。
そこで、私たちは彼の恋愛や人間関係への向き合い方を根本から見直す必要がありました。
直感を見直す方法
これまで、直感を信じるべきではない理由をお話ししましたが、直感を完全に捨て去るべきだとは思っていません。
直感は理由があって存在するからです。
でも、もし、その直感を問い直し、鍛え直すことができたら?
それができたら、きっと素晴らしいですよね。そして、それは確実に可能です。
ただし、その方法は、地味で、時間がかかり、地道な努力が必要です。
ここで、エクスポージャー・セラピー(暴露療法)から、大切な教訓を学ぶことができます。
暴露療法では、不安症、恐怖症、強迫性障害(OCD)などを持つ人に対し、不安を感じるものに立ち向かうことによって、不安は減っていくという事実を体験を通じて教えます。
これは、心理学において非常に再現性の高い、信頼された効果です。
でも、私の考えでは、不安が減るというのは、あくまでプロセスの半分にすぎません。
不安が和らぐと同時に、新たな可能性のためのスペースが生まれます。
再び、人前で話すことを例にあげます。
もしあなたが、人前で話すことへの恐怖や不安を乗り越えたら、その先には、自分の考えを多くの人に伝えることの興奮や喜びが待っているかもしれません。
これは単に不安だけの話ではありません。以下のような心の働きについても同じことが言えます。
・自信のなさ(self-doubt)
・劣等感や不安(insecurities)
・自分の考えが絶対正しいという過信(righteous certainty)
・極端な熱意(fervent enthusiasm)
・無意識に持っている予測(状況に直面する前から抱いている印象)
人がいつもしている無意識の予測
これは、リサ・フェルドマン・バレット(Lisa Feldman Barrett)のような神経科学者たちによって推進されてきた最先端の神経科学の研究によって裏付けられています。
この分野では、私たちの脳は常に無意識の予測を行っていると考えます。
その予測はたいてい以下のものに基づいています。
・過去の経験
・取り込んだ情報
・身体の感覚
・当時の状況
つまり、私たちは日常的に、自覚のない予測を頭の中で常に行っているのです。
情報を実体験と混同する
今のようにかつてないほど大量の情報にアクセスできる時代において、無意識に予測するとき、最も大きく誤ってしまうのは、情報を実体験と取り違えてしまうことです。
他人の意見に過剰に価値を置き、自分自身の経験から得られる学びを過小評価してしまいます。
しかし、外の世界に出て、新しいことをしてみると、失敗を恐れずに挑戦し、失敗を振り返ると、私たちの直感はどんどん鋭くなっていきます。
逆に、新しいことに挑戦せず、外の世界から距離をとり、現状維持に留まってしまえば、私たちの直感は現実からどんどんズレていく可能性が高まります。
これまでに多くのクライアントが自分の衝動を疑い、そして何より、自分の知覚そのものを疑う勇気を持ったおかげで、人生を大きく変えていくのを見てきました。
ここで大切なのは、現実が自分の認識と合っていないとき、現実を疑うのではなく、認識のほうを疑うという姿勢です。
直感にそのまま従うのをやめたスティーブ
さて、スティーブの話に戻りましょう。
彼の恋愛関係が破綻したあとも、私たちは一緒にセラピーを続けました。
彼は次第に、人に好かれようとする直感にそのまま従うのではなく、その反応を少しずつ手放す方法を学んでいきました。
すると、新しい可能性のための余白が生まれました。
それは、たとえば、相手のことを自分の基準で評価することです。
自分がその人をどれだけ魅力的だと感じるか、その人が自分の人生に何をもたらしてくれるか。
そして何より、健全な「与える・受け取る」の関係が築けるかどうか。
彼は、こうした視点を持てるようになりました。
その後、さらに多くの経験と、いくつかの残念なデートを経て、彼は新しい関係を見つけました。
幸いにもその関係は長続きしました。
なぜならそれは、共依存ではなく、ふたりの強い個人が、互いに惹かれ合って築いた関係だったからです。
直感は調整するべきもの
直感は、シンプルな「はかり」のようなものです。
正しく機能させるには、調整(キャリブレーション)が必要です。
本来、直感は信頼しにくいものですが、それを一度も試さずに放置すれば、現実とのズレはどんどん大きくなるでしょう。
おそらく、皆さんも直感に従ってうまくいった経験を何度か思い出せると思います。
でもきっとそれと同じくらい、直感が裏目に出た経験もあるのではないでしょうか?
直感は、迅速で効果的な意思決定を助ける手段になります。
ですがそれは、直感に値する力を自分が身につけた後の話です。
さらに、忘れていけないのは、直感は決して万能ではないということです。
私たちはつねに現実に根ざした行動をすることが重要です。
たとえば、
・実際に人と会って交流する
・心理療法(セラピー)を受ける
・新しいビジネスを始めてみる
・TEDxでスピーチする
このように、世の中に出ていき、その反応から学ぶような行動です。
私たちは、自分の思考、衝動、感情、直感を問い直し、洗練させ、挑戦し、ときには意識的に逆らってみるべきです。
そうやって、直感を人生の複雑な問題を乗り越えるための、非常に強力なツールに育てていくことができます。
それでは、直感を信じるべきか?
その答えは、「はい、ただし、自分にとって信じるに値するものが何かを学んだあとで」です。
//// 抄訳ここまで ////
意思決定に関するほかのプレゼン
ポーカーのチャンピオンが教える意思決定の3つの秘訣(TED)
よりよい決断をする3つの方法、コンピュータのように考える(TED)
決断する力をアップする。自分で決められない理由とうまく決める方法(TED)
情報と自分の気持ちを混同しない
私たちの直感は、バイアスがかかっているので、そのまま信じるべきではないというトークを紹介しました。
これは断捨離中、捨てるものを決めるときにも言えることです。
「好き・嫌い」「ときめく・ときめかない」で家に残すものを決めてしまうと、本当は捨てていいものまで残ってしまいます。
「私はなぜ、これを持っているべきなのか」しっかり考えてから、残すものを見つけたほうが、余計なものを持ちすぎません。
今回のトークで印象的だったのは、情報と経験は違うという点です。
断捨離においても、人が唱える捨て方をたくさん見聞きするより、少しでも実際に自分で捨てる行動をすることが、よい結果につながります。