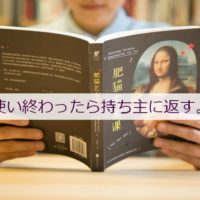ページに広告が含まれることがあります。
狭い家に住んでいるせいで生じがちなストレスとうまく付き合う方法を紹介します。
狭い家で息苦しさを感じるのは、物理的に狭いからだけではありません。視界に入るものが多すぎるせいで、圧迫感や焦りもイライラを生みます。
だからといって、都市部のマンションやアパートでは、スペースに限界があり、そう簡単に広い家に引っ越すことはできません。
家の広さは変えられなくても、考え方や使い方を変えると、もっと心地よく暮らせます。以下に、狭い空間を最大限に楽しむためのヒントを7つ説明します。
1.狭い家のメリットに目を向ける
家の狭さを嘆くのではなく、狭い家のよさや、狭いからこそ得られるものに目を向けましょう。
多くの人が、「広い家=幸福」「ものが多い=豊かさ」という価値観を持っています。でも、狭い家には、広い家にはないメリットが数多くあります。
たとえば、掃除が簡単です。床面積が小さいので、掃除は短時間で終わります。
冷暖房効率もよいので、光熱費も節約できます。
家族との距離が物理的に近いため、コミュニケーションが自然と増え、孤独になりにくいメリットもあります。
「狭い」というネガティブな言葉を、「コンパクトで機能的」と言い換えてみましょう。
小さな家は、管理のコストが低く、快適な状態を維持しやすいです。
こう考えれば、「広い家のほうがいい」、「うちは狭いからだめ」と考えることがなくなります。
2.不用品を徹底的に捨てる
ものが多いと暮らしにくくなるので、いらないものはできるだけ捨てましょう。
ものの置き場所や収納の仕方を工夫しようとするのではなく、「持たないこと」を優先してください。
すでにある収納スペースに入らないものは持たないというルールを作るといいかもしれません。こうすれば、狭いところに無理にものを押し込む必要がなくなります。
「いつか使う」ではなく、「この家に、これを置く必要があるか?」「貴重なスペースを使ってもいいものか?」と考えて、ものを厳選してください。
使わないものはどんなに高価でも、ただ空間を圧迫し、大きなストレスを生みます。
ものを減らした後は、増やさないようにしましょう。
新しいものを1つ買ったら、古いものを1つ捨てるワンインワンアウトを徹底し、ものが増えないようにします。
ものの量がまだまだ多いと思うなら、ワンインツーアウトをするのもおすすめです。
ものをできるだけ持たないこと。これは、狭い家で快適に暮らすための、とても効果的な方法です。
物を減らすのに、ワンインワンアウト(1つ買ったら1つ出す)は本当に効果があるか?
3.色を3色に抑えて視覚的ノイズを減らす
複数の色が氾濫していると視覚的ノイズが増えるので、使う色は3色程度にしておきましょう。
メインカラー(床・壁)、サブカラー(家具)、アクセントカラー(小物)の3色に絞り込むことをおすすめします。
たとえば、私の家は、壁が白、床が薄いグレーなので、家具は黒、白、グレーのどれかを使い、全体をモノトーンにしています。
ベースは白、ベージュ、グレーなどのニュートラルカラーに統一すると、部屋が広く感じられます。
統一感を重視することが基本ですが、季節の花やクッションカバーなど、小さな部分で差し色を楽しむのもいいでしょう。
収納ボックスの色や素材も可能な限り統一し、中身が見えないようにすると、さらに視覚的なノイズが減ります。
洗剤やシャンプーなどのパッケージも、シンプルな色を選ぶか、統一したボトルに移し替えるといいでしょう。
とは言え、いきなりすべてのパッケージを変える必要はありません。買い替えるタイミングで、できるだけ色やデザイン、素材感を合わせることを意識してください。
カラフルなパッケージや雑多なデザインを避けるだけで、脳の疲労が減るので、心が落ち着くようになります。
視覚的ノイズについて詳しいことはこちらの記事を参照してください。シリーズで、家のあちこちにあるノイズを紹介しています⇒視覚的ノイズ(見た目のごちゃつき)を極力なくすコツ(その1)~飾り物を減らす。
4.スムーズに動けるようにする
動線を確保できないとイライラがつのるので、スムーズに動けるようにしましょう。
ものにぶつからないように避けて歩く、扉を開けるたびに邪魔になっているものをどかす。こんなことをしなくてすむように、ものを配置してください。
部屋の真ん中に、ものは置きません。家具は、できるだけ壁に密着させると、部屋の中央にスペースが生まれます。床面積が広がると、部屋が広く感じられるので、圧迫感が軽減されます。
ドアから窓まで、あるいは部屋の隅々まで、まっすぐ歩けるようにものを配置することを心がけてください。
ソファやテーブル、ベッドなどの大きな家具は、キャスター付きや折りたたみ式を選ぶのもいいでしょう。
必要に応じて移動させたり、折りたたんだりして、空間を確保できるようにしておくと、狭い部屋でも窮屈さを感じず、空間を最大限に活用できます。
5.床置きをしない
4番に書いたように、床が見えていると、より広く感じられます。
そこで、理由なくものを床に置かないようにしましょう。
床置きしないために、以下を徹底してください。
・床に直置きしがちなゴミ箱や本、カゴは、本当に必要かどうか検討する。いらないなら捨てる。
・家に置くしかないなら、壁面収納や吊り下げ収納にする(床面積を使わない収納を検討する。ただしやりすぎない)。
床にものがなければ、掃除もラクになるので、家事のストレス軽減にも役立ちます。
床置きしない人になるには?~スッキリした部屋を作るために(1)
6.自分のスペース/時間を確保する
狭い家では、家族との距離が近くなるので、常に誰かの気配を感じる、一人になれないという不満があるかもしれません。
そんなときは、物理的・心理的な境界線を作りましょう。
ワンルームやリビングの一角に、簡単なパーティションをもうけます。たとえば、背の高い観葉植物、布製のスクリーンなどを利用すれば、一時的なプライベートスペースを作ることができます。
また、「今は話しかけないでほしい」という合図や時間帯を決めておき、ひとり時間を確保します。
たとえば、「ヘッドホンをつけているときは、ひとりで集中したい時間」「朝9時から12時までのリビングは仕事優先」といったルールを作って家族と共有します。
家族が多い場合、ストレスの主な原因は音です。ノイズキャンセリングタイプを使うと、集中しやすいのでおすすめです。
家族それぞれが安心して集中したり、リラックスしたりできる時間と空間を確保できるよう、お互いに協力しましょう。
7.家の外を積極的に活用する
家の外にある施設を、自分の家の延長として積極的に利用します。
すべての活動を家の中で完結させようと思うと、スペースが足りないことに不満を抱きます。
仕事や勉強は必ずしも自宅でする必要はありません。
自宅で集中できない作業は、コワーキングスペース、カフェ、図書館など、外部のスペースを自分の書斎と見立てて活用してください。
こうすると、自宅のスペースを仕事道具で埋めなくてすみます。
趣味や運動も同じように考えましょう。
自宅に置き場のない大きな趣味の道具は、レンタルスペースやジムのロッカーを活用し、家に持ち込まないようにします。
運動は公園やジムでしましょう。
私は、室内にはプラントや花びんは置かず、花や植物は、窓から眺めたり、朝散歩しているときに、外にあるものを見てなごんでいます。
もし、必要なものがどうしても自宅に入り切らないなら、トランクルームなどの外部の収納スペース使ってください。
ただし、何でもトランクルームに収納しようとするのではなく、「本当に必要だけど、今すぐは使わないもの」だけを厳選して預けてください。安易に外部収納を使うと、ものが増えてしまいます。
◆「狭い家に住む」関連記事もどうぞ:
狭い家で暮らす7つのメリット – コンパクトな暮らしを楽しむために。
物の置き場所が決まらず部屋がカオスです。どうしたらいいですか?
狭い賃貸マンションで子どもが3人いて、ものが多くてスッキリ暮らせない。ストレスでいっぱいです←質問の回答。
******
狭い家で快適に暮らす秘訣を7つ紹介しました。
狭い家から生じるストレスは、ものの量と配置、自分の考え方から生まれることが多いもの。家の狭さだけが問題なのではありません。
今回紹介した7つの行動は、広い家に引っ越さなくても、今日からできる行動ばかりです。ぜひ、試してください。
特におすすめしたいのは以下の2点です。
・狭い家のメリットに目を向ける
・ものを徹底的に減らす
狭い空間でも、工夫と考え方次第で、身軽に暮らせます。
スペースをを手に入れようとするよりも、「心地よさ」を増やしてください。