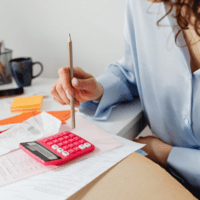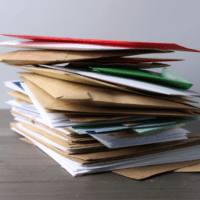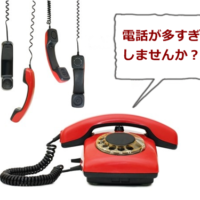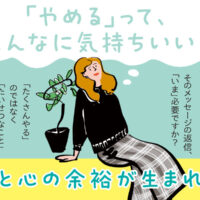ページに広告が含まれることがあります。
アンチエイジングシリーズ。今回は脳の若さを保つ方法を7つお伝えします。認知症予防のためにも、脳の健康によい生活を送りましょう。
アンチエイジングとは老化の原因を抑制して、からだの衰えを遅くすること。年をとっても若々しくいるために、さまざまな手を打つことです。
人間のすべての機能を司っているのは言うまでもなく脳です。脳を若く保つことはアンチエイジングの要です。
脳のアンチエイジングにはこんなことをすると効果的です。
1.運動をする
脳の若々しさを保つのに1番効果的なのは、からだを動かすこと、つまり運動です。脳トレなどのゲームをする前に、まず運動をして、脳を活性化させてください。
運動をすると血液の循環がよくなり、栄養や酸素も脳に行くので、脳内の健康を保つのに最適なのです。
どんな運動をしても、心拍数があがりますが、有酸素運動(エアロビクス、ジョギングなど)がおすすめです。これにちょっぴり無酸素運動、つまり筋トレを組み合わせるとベスト。
年をとると脳にあるニューロンから出ている樹の枝みたいな物が次第に失われていきます。
ニューロンとは、神経のびりびりを伝える脳内の細胞。枝みたいなのが出ていて(もちろんすごく小さいです)、これがほかの細胞とつながって、神経のビリビリを伝えることでさまざまな情報を伝達しています。
この神経回路は「考えること」に不可欠ですが、残念ながら、高齢になると少しずつ減ってしまいます。
運動によりこの現象を防ぐことができます。
お年寄りが運動をするのは、筋肉や関節のためだけではないのです。
運動は老化予防のみならず、病気予防のためにも不可欠。心臓病、肥満、糖尿病などになってしまったら、運動することもままなりません。
2.色のついた野菜や果物を食べる
脳を若々しく保つには、食べ物にも気を使う必要があります。抗酸化物質がたくさん含まれている食品を食べるのが有効です。
しみやしわの予防に、野菜やフルーツを食べるといい、とはよく聞く話です。野菜や果物には抗酸化物質がたくさん含まれているからです。
老化は活性酸素(おもにフリーラジカル)で細胞が酸化されることです。フリーラジカルはニューロンをこわしてしまうのです。
フリーラジカルについてはこちらの記事に詳しく書いています⇒アンチエイジングならブルーベリーで決まり~8つの美容と健康効果、知っていますか?
抗酸化物質はその名の通り、フリーラジカルを中性にして、酸化をふせいでくれます。
抗酸化物質が豊富なのは、緑黄色野菜や、果物。ほかには、豆や小麦胚芽、ナッツ、スパイスなど。色素や辛味の成分に抗酸化物質が含まれています。
このような食品を食べるだけでなく、全般的にヘルシーな食生活をすることも大切です。
太りすぎていると内臓すべてに負担がかかりますが、脳にも同じように負担がかかります。
3.脳を使う
脳の情報処理能力や記憶力は30歳から次第に衰えていきます。しかし、鍛えれば若い脳を保つことができます。そのためには脳を使うことが不可欠です。いわゆる脳トレです。
脳にチャレンジングなことならなんでもいいです。ちょっと複雑な工作をしたり、ジグソーパズルをしたり、絵を描いたり。新しい技術を学ぶのも効果的。語学や、社交ダンス、楽器の演奏、箱庭作りなど。もちろん、昔習った数学を学び直して、問題を解くのもいいです。
とにかく頭は使わないとぼけます。意欲的に新しいことを学んでいけば、脳細胞の連携を強化できます。新しい細胞すらできます。
いつもと同じような生活をしているのではなく、常に何か新しい、自分にとってちょっとチャレンジングなことをすればいいのです。
集中が必要で、やっていて楽しく、達成感があることを選んでください。
お年寄りは座ってテレビを見るのが好きですが、これは脳には全然よくないです。
テレビを見ていると、一応脳が刺激されますが、たぶん何も新しいことを学ぼうとしてはいないでしょう。それより、ピンポンなんかするほうが脳にはよっぽどいいです。
テレビを見るなら、ドラマを1つ見たら、テレビを切って、そのドラマの内容を要約して、人に聞かせるというようなことをすれば脳を使うことになります。
ニュースを見たら、翌日、きのうはどんなニュースがあったのか、5本ぐらい自分の感想とともに孫に話して聞かせるとか。
ニュースを見ても、ほとんど忘れてしまいますが、それを思い出そうとすることが脳トレになります。
アンチエイジングな生活習慣はこちらにも書いています⇒意外と知られていない、アンチエイジング効果のある7つの生活習慣
4.ストレスは最小限にして心穏やかに過ごす
ストレスは脳細胞によくありません。脳細胞に限ったことではありませんが。脳には適度な刺激が必要ですが、これがストレスになると逆効果です。
ストレスが多いと、学習や記憶といういわゆる認知のプロセスが大幅に損なわれます。
特にストレスに弱いのは海馬(かいば)です。ここは短期記憶を司ると考えられている「記憶」にはかなり重要な場所。いつもストレスを感じていると、海馬がしっかり活動しないそうです。
何かすごく衝撃的なことが起こると、メンタルブロックが起きて、何も考えられなくなりますが、恒常的にストレスを感じていると、似たようなことがもっと小さなレベルで起こるのではないでしょうか。
運動をするとストレス解消になりますが、同時に、ヨガや瞑想など、静かな時間を持つことも脳の健康を保つのに大切です。
瞑想のやり方はこちら⇒『必要なのは10分間の瞑想だけ』~物より心が大切です(TED)
日常生活のストレスの多くが、ガラクタから来ていますから、断捨離も有効です。ガラクタがストレスのもとになる理由⇒物が多いとストレスがたまる7つの理由
ほかにも取り除けるストレスの元があれば取り除き、取り除けないものに対しては、自分の考え方を変えて、できるだけ、心穏やかに、幸せに暮らすと、脳の衰えを防ぐことができます。
5.適切な睡眠をとる
時々、静かな時間を過ごすことが脳の健康によいのですが、人がもっとも静かに過ごす行動は「寝ること」です。
夜しっかり眠っている人のほうが、さまざまな問題をよりクリエイティブに解くことができる、という研究があります。
睡眠不足の頭で、新しいことを学ぼうとしても、効率は悪く、ストレスが増えるばかりです。
よって、脳に刺激を与える前に、しっかり寝ておくことが大切です。夜ぐっすり寝ておくと、脳はより複雑な情報を処理することができるのです。
睡眠についてはこちらもどうぞ⇒なぜ人は眠るのか?睡眠の大切さを忘れていませんか?(TED)
6.若いうちから脳の健康を保つように心がける
アルツハイマーに代表される認知症は、年をとって急になるのではなく、「少なくとも25年前には、初期症状が見られる」という研究があります。
また、「20代の脳の状態から、将来、アルツハイマーを発生するかどうか、かなり予想できる」という研究もあります。とはいえ、これは理論上のことです。ある人の脳を20代から認知症になるまで調べるなんて、なかなかできることではありません。
ほかのリサーチでは、中年のとき、健康な人のほうが、65歳になったとき、アルツハイマーにかかるリスクが40%低い、という結果が出ています。
そこで、「私はまだ若いから関係ない」とは思わず、40歳すぎたら、多少は脳の健康についても考え、ガラクタは捨てて、睡眠はしっかりとり、運動をするという健康的なライフスタイルにシフトしたほうがいいと思います。
運動といってもそんなにすごいことをする必要はありません。ふだん全く運動をしない人は、歩くだけでも大きく違います。
ウォーキングのメリットはこちら⇒ウォーキングはダイエットと健康に不可欠、暮しの質も高くなる
認知症になると、自分では何もわからないわけですから、「かえって幸福である」という考え方もあります。ですが、やはりできれば認知症にはならず、最後まで自分の人生を全うしたほうがよいですよね。
☆脳の若さを保つアクティビティを7つ紹介しています⇒健康的な生活が嫌いな人に贈る、楽しみながらボケない脳をつくる7つの方法。
7.年をとることを悲観しない
記憶能力などは年をとると確実に衰えますが、年をとるにしたがって、脳が得意になることもあります。
年をとった人のほうが「知恵」があると言われますが、この点についても、科学的に研究が進んでいます。
年をとった人の脳には、無数の「社会的なシナリオ」、要するに「経験」が刻み込まれていて、何か問題があったときに、さっと取り出せるようになるそうです。また、高齢者の脳は情報を組み合わせたり、統合するのが得意です。
若者よりお年寄りのほうがさまざまな社会的経験があり、それが知恵となって、脳内に集積されているのです。当たり前といえば当たり前です。「亀の甲より年の功」です。
この知恵は50代ごろから発揮されます。大企業の役員や政治家などで、すばらしいアドバイスをする人は、50代、60代以降の人が多いです。
このような人たちは、単に会社に長くいたからその地位にいるわけではなく、会社の舵とりができる知恵があるから、そのポストにいるのです。
また、昔から「長老」と呼ばれる人たちがさまざまな組織で活躍しています。
現代社会は、「なんでも若い方がいい」という考え方が主流です。ですが、実は年をとってからよくなることもあるのです。
この点について忘れず、若さにしがみつかないことも、脳全体の若さを保つのに効果的です。